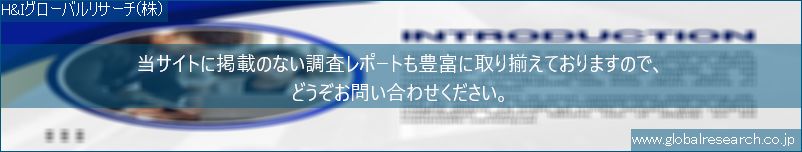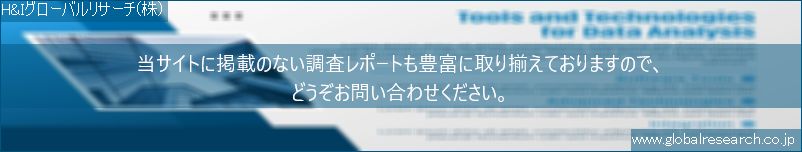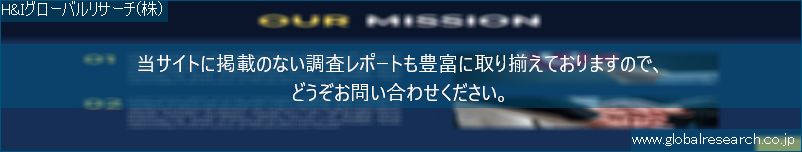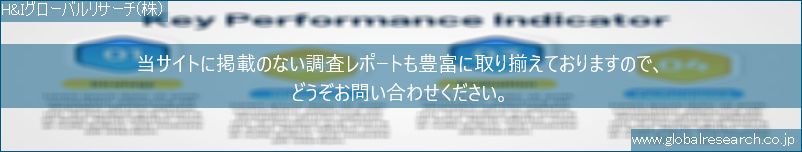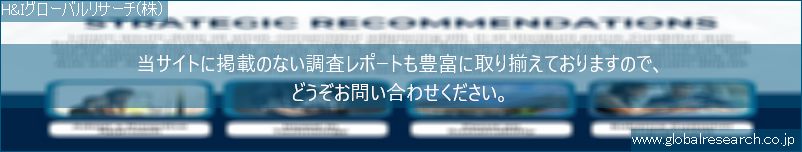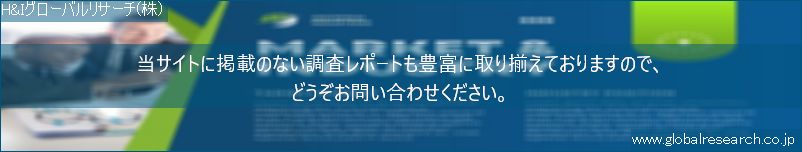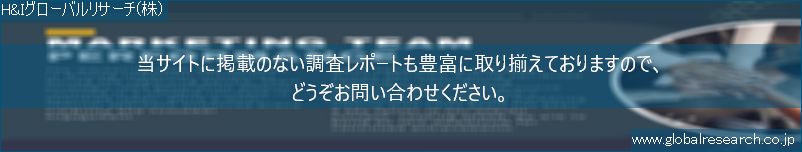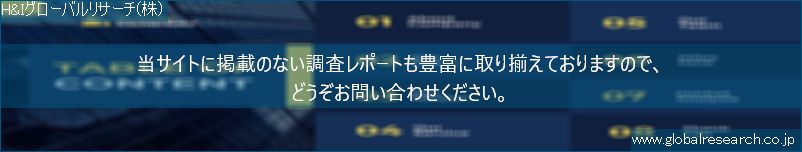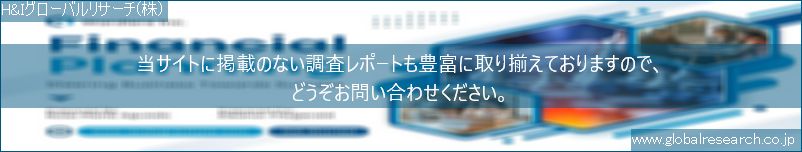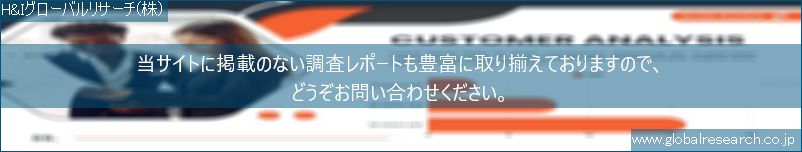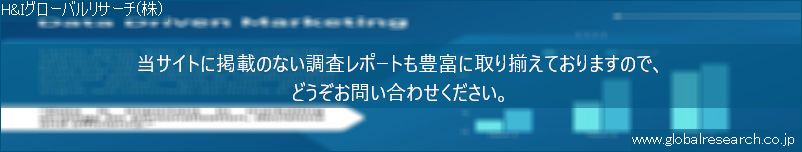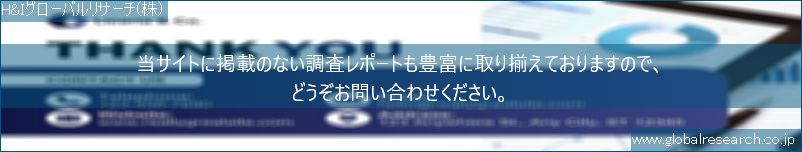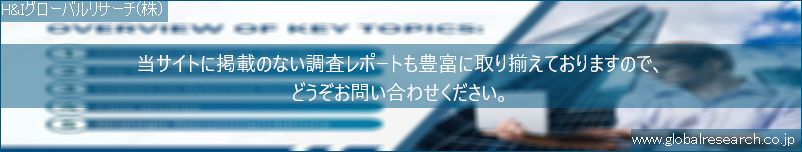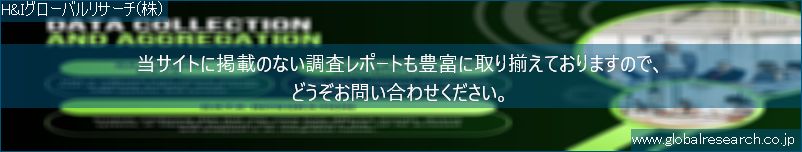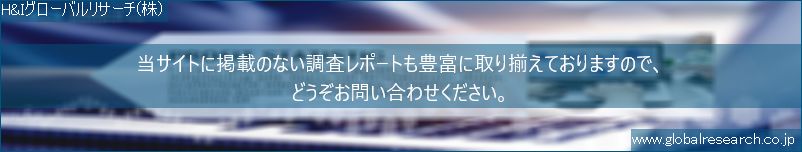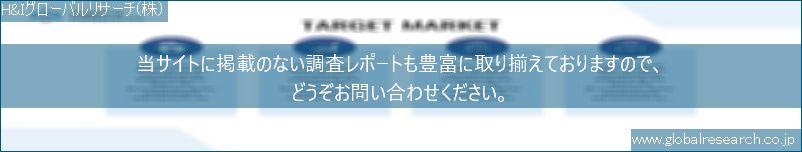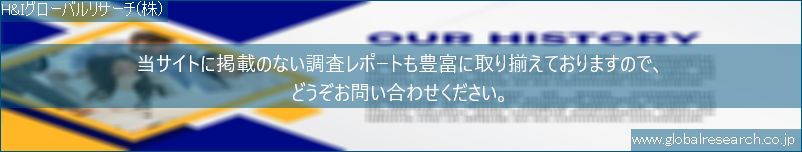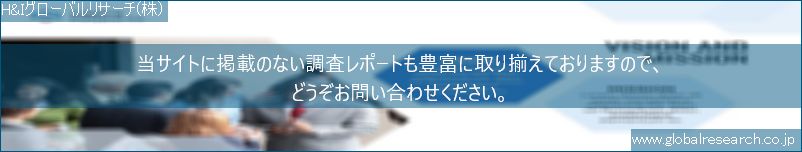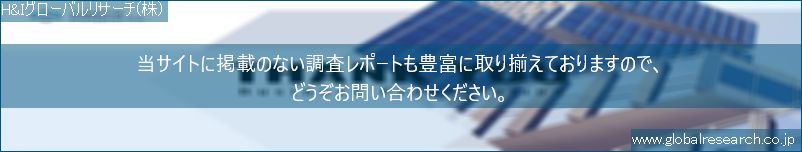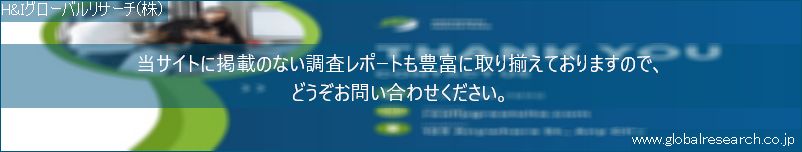日本の細胞・遺伝子治療市場規模は2024年に7億2700万米ドルとなった。今後、IMARC Groupは、同市場が2033年までに20億1,600万米ドルに達し、2025年から2033年にかけて12%の年平均成長率を示すと予測している。日本市場は、バイオテクノロジーの進歩、個別化医療への注目の高まり、再生療法に対する政府支援の増加によって牽引されている。新規細胞・遺伝子治療の普及は、高齢化、遺伝性疾患や慢性疾患の頻度増加、研究開発(R&D)への多額の投資によってさらに加速している。
バイオテクノロジーにおける注目すべき科学的ブレークスルーと、オーダーメイド医療の重視の高まりが、日本における細胞・遺伝子治療市場を後押ししている。CRISPR療法やCAR-T療法を含む先端技術により、従来は不治の病と考えられていた疾患に対しても、正確な遺伝子改変や新規治療が可能となる。例えば、2023年12月、ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社は、B細胞成熟抗原(BCMA)指向性キメラ抗原受容体(CAR)T細胞免疫療法であるアベックマ®(イデカブタジェンビクリューセル)の適応追加の製造販売承認を取得したと発表した。これは特に、免疫調節剤、プロテアソーム阻害剤、抗CD38抗体を含む少なくとも2種類の前治療を受けた再発または難治性の多発性骨髄腫(RRMM)患者を対象としています。特に再生医療安全法(ASRM)による再生医療の早期承認プロセスなど、国の積極的な規制構造がイノベーションを促進し、製品の商業化を加速させている。さらに、助成金や研究機関との協力という形での政府の支援は、遺伝子治療や細胞治療の開発を促進し、日本が再生医療における世界的リーダーとしての地位を確立している。
日本では、高齢化と遺伝性疾患や慢性疾患の増加により、細胞・遺伝子治療への需要がさらに高まっている。がん、心臓病、珍しい遺伝子異常などの病気の有病率の上昇により、患者は治癒の可能性のある最先端の治療法を求めている。国内外の製薬会社は研究開発に多額の投資を行っており、これが最先端治療の強力なパイプラインを支えている。例えば2024年3月、人工多能性幹細胞(iPS細胞)の産業界への移転を目指す公益財団法人CiRA財団と、医療技術企業のテルモ・ブラッド・アンド・セル・テクノロジーズ(テルモBCT)は、様々な新規治療へのiPS細胞の普及を目指した提携を発表した。テルモBCTの実現可能な技術と細胞治療製造の専門知識、そしてCiRA財団の最先端のiPS細胞に関する知識の助けを借りて、両社はiPS細胞由来の治療のための自動化された臨床的に適切なワークフローを構築することを目指しており、これは細胞・遺伝子治療(CGT)分野のゲームチェンジャーとなる可能性がある。さらに、産学連携は臨床研究を加速させ、革新的な治療法を確実に提供するために不可欠であり、日本の細胞・遺伝子治療市場の拡大を後押しするものである。
日本の細胞・遺伝子治療市場の動向:
バイオテクノロジーの著しい進歩
遺伝子編集、CRISPR、CAR-Tなどの先端技術は、標的を絞った新規治療法の創出を推進する。これらの開発により、日本は細胞・遺伝子治療のリーダーとしての地位を確立し、慢性疾患や遺伝性疾患の効率的な治療が可能になった。例えば、2023年12月、神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科の一部でもあり、カスタムDNA合成と遺伝子治療バイオファウンドリーサービスを提供する合成生物学の新興企業であるシンプロジェン株式会社と、イチョウ・バイオワークス株式会社は、拘束力のない覚書(MOU)を締結したと発表した。シンプロジェンとイチョウは、日本における遺伝子治療プラットフォームサービスとDNA生産のグローバルな開発を促進するために協力することを目指しています。
慢性疾患と遺伝性疾患の増加
日本では、がん、心血管疾患、希少遺伝性疾患の罹患率が高く、根治療法に対する強い需要が生じている。細胞・遺伝子治療はアンメット・メディカル・ニーズに対応し、従来の治療法では限界がある患者に革新的な選択肢を提供する。例えば、2024年9月、PHC株式会社の一部であるバイオメディカル事業部は、研究者が細胞培養における代謝変化を可視化することを可能にするライブ細胞代謝分析装置LiCellMoの商業的発売を発表した。LiCellMoは、PHC独自の高精度インラインモニタリング技術を利用しており、サンプリングのために実験を中断することなく、培養液中の細胞代謝物のエンドレス測定を支援する。
政府と産業界からの投資
政府からの多額の資金援助、大学との共同研究、産業界との提携が研究開発の原動力となっている。こうした取り組みは、治療パイプラインを拡大し、臨床試験を進め、革新的な治療法の利用可能性を確保し、世界の再生医療市場における日本の地位を押し上げている。例えば、2024年1月、株式会社日本政策投資銀行(DBJ)は、4BIO Partners LLPが運営するバイオベンチャー・ファンド、4BIO Ventures III LPとの投資契約を発表した。4BIOベンチャーズファンドは、革新的な治療法を開発し、アンメットメディカルニーズの解決に貢献するアーリーステージのバイオベンチャーにフォーカスしています。ロンドンに本社を置き、北米、欧州、日本、アジアのその他の地域を含むグローバルネットワークを持つ同社は2014年に設立され、以来、細胞・遺伝子治療、RNAベース医療、標的治療、マイクロバイオームを含む新規創薬モダリティを開発するバイオベンチャーへの投資に尽力してきた。
日本の細胞・遺伝子治療産業のセグメンテーション:
IMARC Groupは、日本の細胞・遺伝子治療市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2025年から2033年までの国・地域レベルの予測を提供しています。市場は治療の種類別、適応症別、デリバリーモード別、エンドユーザー別に分類されています。
治療種類別分析:
– 細胞療法
o 幹細胞
o 非幹細胞
– 遺伝子治療
細胞治療は、がん、自己免疫疾患、変性疾患など様々な疾患の治療が可能なことから、大きなシェアを占めている。幹細胞やCAR-T療法を含む再生医療は、高齢化社会と慢性疾患の蔓延を背景に、日本で高い需要がある。日本の強固な研究インフラと、再生医療安全性法の早期承認を含む支援的な規制環境は、細胞治療の開発と採用をさらに促進し、市場でのリーダーシップを確固たるものにしている。
遺伝子治療は、遺伝性疾患や希少疾患に対して長期的な治癒可能な解決策を提供する可能性があるため、市場をリードしている。CRISPRのような遺伝子編集技術の進歩と、日本における遺伝性疾患の有病率の増加が採用を後押ししている。市場の浸透は、新規治療に対する政府の支援と臨床試験活動の拡大によって高まっている。研究開発への多額の投資により、遺伝子治療は治療用途を拡大し、日本の再生医療市場における主導的地位を保証している。
適応症別分析
– 心血管疾患
– 腫瘍疾患
– 遺伝子疾患
– 感染症
– 神経疾患
– その他
心血管疾患は、日本の高齢化社会における有病率の高さから、大きなシェアを占めている。幹細胞治療を含む細胞治療は、損傷した心臓組織を修復し、長期にわたる心臓疾患の予後を改善する再生ソリューションを提供する。心血管疾患は主な死因の一つであるため、新規かつ効果的な治療法に対するニーズは高まっている。心血管系疾患に対する細胞治療や遺伝子治療の利用は、再生医療に対する政府の資金援助や、この分野における臨床研究の活発化によっても後押しされている。
腫瘍疾患は、日本、特に高齢者人口における癌の発生率の上昇に起因する。CAR-Tや遺伝子編集技術など、複雑ながんに対する先進治療は、生存率を高める個別化されたオーダーメイドの治療を提供する。日本は、その強力な規制環境と迅速な承認を通じて、がんに特化した細胞・遺伝子治療のイノベーションを促進している。研究開発費の増加や、バイオテクノロジー企業と学術機関との提携も、こうした革新的ながん治療薬へのアクセスや普及を向上させている。
遺伝性疾患は、遺伝性疾患の根本原因に対処する遺伝子治療の可能性により、大きなシェアを占めている。CRISPRやその他の遺伝子編集技術のような治療法は、日本では希少な遺伝性疾患が診断されるようになり、治療法を提供する。遺伝性疾患研究に資金を提供する政府のプログラムと、拡大する遺伝子治療パイプラインが、商業的な拡大を後押ししている。強化された診断能力と的を絞った治療アプローチにより、遺伝子治療は日本における遺伝性疾患の治療においてその存在感を増している。
デリバリーモード別分析
– インビボ
– 生体外
生体内遺伝子治療は、遺伝物質を患者の細胞内に直接導入する能力により、遺伝性疾患、癌、希少疾患などの病態に対して正確で効果的な治療を提供することができる。アデノ随伴ウイルス(AAV)などのウイルスおよび非ウイルス送達システムの進歩は、治療の効率と安全性を高めている。日本の支持的な規制の枠組みや、生体内治療に焦点を当てた臨床試験の増加は、採用をさらに後押しする。長期的あるいは根治的な治療効果が期待できることから、同市場における主導的な役割は確固たるものとなっている。
生体外療法は、体外で細胞の遺伝子組み換えを行ってから患者に再導入するため、高い精度と制御された治療効果が得られることから、大きなシェアを占めている。がんに対するCAR-T療法はその顕著な例であり、顕著な有効性を示している。日本の再生医療に関する専門知識と研究開発投資の拡大は、生体外アプローチにおける進歩を後押しする。個別化治療への需要の高まりと、細胞加工のための強固なインフラにより、生体外療法はその用途を拡大し続け、市場での強い存在感を維持している。
エンドユーザー別分析:
– 病院
– がん治療センター
– 製薬・バイオテクノロジー企業
– その他
病院は、特にCAR-T療法や幹細胞療法のような複雑な治療において、細胞療法や遺伝子治療の一次医療機関としての役割を担っている。高度なインフラを備えた病院は、こうした治療に関わる複雑なプロセスを処理している。日本では高齢化が進み、慢性疾患の有病率が上昇しているため、病院を拠点とした治療に対する需要が高まっている。臨床試験や治療提供のための製薬会社との提携は、市場でのシェアをさらに高めている。
日本におけるがん罹患率の上昇により、がん治療センターが大きなシェアを占めている。専門センターは、CAR-Tのような高度な治療を実施するのに理想的であり、専門家による対応とモニタリングが必要である。これらのセンターはがん治療に重点を置いているため、個別化された革新的なソリューションを提供する上で極めて重要な存在となっている。臨床試験や治療展開のためのバイオテクノロジー企業との強力なパートナーシップは、がん治療センターががん領域における細胞・遺伝子治療導入のための重要なハブであり続けることを確実なものにしている。
製薬企業とバイオテクノロジー企業は、細胞療法と遺伝子療法の開発と商業化をリードしている。これらの企業の強力な研究開発能力、資金調達へのアクセス、革新的な治療法を推進する専門知識が市場を牽引している。日本では、これらの企業は病院や研究機関と積極的に協力し、臨床試験や薬事承認を拡大している。製造、流通、技術の進歩におけるこれらの企業の役割は、細胞・遺伝子治療市場における優位性を確実なものにしており、最先端の治療に対する需要の高まりに対応している。
地域別分析:
– 関東地方
– 関西/近畿
– 中部・中部地方
– 九州・沖縄地方
– 東北地方
– 中国地方
– 北海道地方
– 四国地方
東京を含む関東地方は、高度な医療インフラ、最先端の研究機関、バイオテクノロジーの中心地として市場を牽引している。この地域は、臨床試験や細胞・遺伝子治療の開発のために多額の投資を集めている。人口密度が高く、最先端の治療に対する需要が高い関東地方は、今後も市場成長の中心であり続ける。
大阪と京都を擁する関西は、バイオテクノロジーと製薬の中心地である。この地域の有名大学や研究機関が再生医療のイノベーションを促進している。この地域は、がんや遺伝性疾患の治療に力を入れており、細胞治療や遺伝子治療の開発・実施におけるリーダーシップを支えている。
高度な製造技術で知られる中部は、細胞・遺伝子治療産業を支える研究・生産施設を提供している。名古屋のような主要都市はバイオテクノロジー開発に投資しており、製品開発や臨床研究を向上させている。この地域は技術革新に重点を置いているため、治療法の導入における役割の高まりが保証されている。
九州・沖縄は、地域医療の進歩に対する政府の支援から恩恵を受けている。再生医療や慢性疾患治療のための専門施設に関する研究の増加により、この地域は、特に老化に関連した症状に対処するための細胞・遺伝子治療開発の拠点として成長しつつある。
東北地方は再生医療研究に重点を置いており、国や大学との連携により資金が提供されている。この地域が最先端の医療、特に珍しい病気に対する治療に重点を置いていることは、細胞・遺伝子治療が都市部と地方の両方でますます普及している理由の一助となっている。
中国地方は、最先端医薬品へのアクセス拡大を視野に入れ、細胞・遺伝子治療の研究開発に資金を投入している。特にがんや循環器疾患の治療において、地域組織とバイオテクノロジー企業の協力が成長を後押ししている。
北海道は研究と臨床試験を重視し、学術機関を活用して遺伝性疾患や希少疾患の遺伝子治療を推進している。この地域の最先端治療の導入は、地域投資と医療意識の高まりに支えられている。
四国は、遺伝子治療や細胞治療を促進するための医療システムの整備を進めている。この地域は、研究機関とバイオテクノロジー企業とのパートナーシップの拡大により、遺伝性疾患や慢性疾患に対する最先端の治療法を国民に提供することに力を注いでいる。
競争環境:
日本の細胞・遺伝子治療市場は競争が激しく、ノバルティス、ブリストル・マイヤーズ スクイブ、ギリアド・サイエンシズのようなグローバル企業とともに、武田薬品工業、アステラス製薬、富士フイルムセルラー・ダイナミクスなどの大手企業がしのぎを削っている。これらの企業は、再生医療、希少疾患、がんに対する最先端の治療法の創出を重視している。研究機関、企業、学界が一体となってイノベーションを推進しており、これは日本の有利な規制環境に助けられている。外資系企業が提携を結んで足場を固める一方、国内企業は現地の専門知識や政府の支援を活用している。治療薬のパイプラインの増加と臨床試験活動の活発化は、急速に発展するこの市場での競争をさらに激化させている。例えば、帝人株式会社は2024年10月、シンガポールのバイオテクノロジー企業ヒレマン・ラボラトリーズと戦略的国際商業協力を展開する覚書を締結したと発表した。この提携の目的は、細胞・遺伝子治療業界の開発・製造受託機関(CDMO)事業の成長を促すことである。
最新のニュースと展開
– 2024年9月、AGC Biologicsの親会社であるAGCとメディネットとの間で、細胞治療CDMO事業における提携契約が締結された。この提携の一環として、AGCはメディネットに人材を派遣し、日本のベンチャー企業やアカデミアとの提携経験が豊富なメディネットの事業を支援することで、日本における同事業の知見を深めるとともに、2026年に予定されているAGCバイオロジクス横浜事業所での細胞医療CDMOサービスの開始(一部は2025年開始)に備える。
– 2024年7月、国立がん研究センター(東京都中央区)とペンシルバニア大学(米国ペンシルバニア州フィラデルフィア市)は、ケモカイン受容体CCR4を標的とするキメラ抗原受容体T細胞療法(CCR4 CAR-T細胞療法)に関する特許権を、国立がん研究センター発のベンチャー企業であるアーク・セラピィズ株式会社にライセンスした。本契約により、アークセラピィズ株式会社は、日本で流行している成人T細胞白血病/リンパ腫(ATLL)*3を含むT細胞がんを標的とした細胞治療の研究開発を開始することになります。さらに、CCR4 CAR-T細胞療法の固形がんへの応用の可能性も追求する。
本レポートで扱う主な質問
1.細胞・遺伝子治療とは何か?
2.日本の細胞・遺伝子治療市場の規模は?
3.2025-2033年の日本の細胞・遺伝子治療市場の予想成長率は?
4.日本の細胞・遺伝子治療市場を牽引する主要因は何か?
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Japan Cell and Gene Therapy Market - Introduction
4.1 Overview
4.2 Market Dynamics
4.3 Industry Trends
4.4 Competitive Intelligence
5 Japan Cell and Gene Therapy Market Landscape
5.1 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
5.2 Market Forecast (2025-2033)
6 Japan Cell and Gene Therapy Market - Breakup by Therapy Type
6.1 Cell Therapy
6.1.1 Overview
6.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.1.3 Market Segmentation
6.1.3.1 Stem Cell
6.1.3.2 Non-Stem Cell
6.1.4 Market Forecast (2025-2033)
6.2 Gene Therapy
6.2.1 Overview
6.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.2.3 Market Forecast (2025-2033)
7 Japan Cell and Gene Therapy Market - Breakup by Indication
7.1 Cardiovascular Disease
7.1.1 Overview
7.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.1.3 Market Forecast (2025-2033)
7.2 Oncology Disorder
7.2.1 Overview
7.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.2.3 Market Forecast (2025-2033)
7.3 Genetic Disorder
7.3.1 Overview
7.3.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.3.3 Market Forecast (2025-2033)
7.4 Infectious Disease
7.4.1 Overview
7.4.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.4.3 Market Forecast (2025-2033)
7.5 Neurological Disorder
7.5.1 Overview
7.5.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.5.3 Market Forecast (2025-2033)
7.6 Others
7.6.1 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.6.2 Market Forecast (2025-2033)
8 Japan Cell and Gene Therapy Market - Breakup by Delivery Mode
8.1 In-Vivo
8.1.1 Overview
8.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.1.3 Market Forecast (2025-2033)
8.2 Ex-Vivo
8.2.1 Overview
8.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.2.3 Market Forecast (2025-2033)
9 Japan Cell and Gene Therapy Market - Breakup by End User
9.1 Hospitals
9.1.1 Overview
9.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.1.3 Market Forecast (2025-2033)
9.2 Cancer Care Centers
9.2.1 Overview
9.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.2.3 Market Forecast (2025-2033)
9.3 Pharmaceutical and Biotechnology Companies
9.3.1 Overview
9.3.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.3.3 Market Forecast (2025-2033)
9.4 Others
9.4.1 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.4.2 Market Forecast (2025-2033)
10 Japan Cell and Gene Therapy Market – Breakup by Region
10.1 Kanto Region
10.1.1 Overview
10.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.1.3 Market Breakup by Therapy Type
10.1.4 Market Breakup by Indication
10.1.5 Market Breakup by Delivery Mode
10.1.6 Market Breakup by End User
10.1.7 Key Players
10.1.8 Market Forecast (2025-2033)
10.2 Kansai/Kinki Region
10.2.1 Overview
10.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.2.3 Market Breakup by Therapy Type
10.2.4 Market Breakup by Indication
10.2.5 Market Breakup by Delivery Mode
10.2.6 Market Breakup by End User
10.2.7 Key Players
10.2.8 Market Forecast (2025-2033)
10.3 Central/ Chubu Region
10.3.1 Overview
10.3.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.3.3 Market Breakup by Therapy Type
10.3.4 Market Breakup by Indication
10.3.5 Market Breakup by Delivery Mode
10.3.6 Market Breakup by End User
10.3.7 Key Players
10.3.8 Market Forecast (2025-2033)
10.4 Kyushu-Okinawa Region
10.4.1 Overview
10.4.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.4.3 Market Breakup by Therapy Type
10.4.4 Market Breakup by Indication
10.4.5 Market Breakup by Delivery Mode
10.4.6 Market Breakup by End User
10.4.7 Key Players
10.4.8 Market Forecast (2025-2033)
10.5 Tohoku Region
10.5.1 Overview
10.5.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.5.3 Market Breakup by Therapy Type
10.5.4 Market Breakup by Indication
10.5.5 Market Breakup by Delivery Mode
10.5.6 Market Breakup by End User
10.5.7 Key Players
10.5.8 Market Forecast (2025-2033)
10.6 Chugoku Region
10.6.1 Overview
10.6.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.6.3 Market Breakup by Therapy Type
10.6.4 Market Breakup by Indication
10.6.5 Market Breakup by Delivery Mode
10.6.6 Market Breakup by End User
10.6.7 Key Players
10.6.8 Market Forecast (2025-2033)
10.7 Hokkaido Region
10.7.1 Overview
10.7.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.7.3 Market Breakup by Therapy Type
10.7.4 Market Breakup by Indication
10.7.5 Market Breakup by Delivery Mode
10.7.6 Market Breakup by End User
10.7.7 Key Players
10.7.8 Market Forecast (2025-2033)
10.8 Shikoku Region
10.8.1 Overview
10.8.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
10.8.3 Market Breakup by Therapy Type
10.8.4 Market Breakup by Indication
10.8.5 Market Breakup by Delivery Mode
10.8.6 Market Breakup by End User
10.8.7 Key Players
10.8.8 Market Forecast (2025-2033)
11 Japan Cell and Gene Therapy Market – Competitive Landscape
11.1 Overview
11.2 Market Structure
11.3 Market Player Positioning
11.4 Top Winning Strategies
11.5 Competitive Dashboard
11.6 Company Evaluation Quadrant
12 Profiles of Key Players
12.1 Company A
12.1.1 Business Overview
12.1.2 Services Offered
12.1.3 Business Strategies
12.1.4 SWOT Analysis
12.1.5 Major News and Events
12.2 Company B
12.2.1 Business Overview
12.2.2 Services Offered
12.2.3 Business Strategies
12.2.4 SWOT Analysis
12.2.5 Major News and Events
12.3 Company C
12.3.1 Business Overview
12.3.2 Services Offered
12.3.3 Business Strategies
12.3.4 SWOT Analysis
12.3.5 Major News and Events
12.4 Company D
12.4.1 Business Overview
12.4.2 Services Offered
12.4.3 Business Strategies
12.4.4 SWOT Analysis
12.4.5 Major News and Events
12.5 Company E
12.5.1 Business Overview
12.5.2 Services Offered
12.5.3 Business Strategies
12.5.4 SWOT Analysis
12.5.5 Major News and Events
13 Japan Cell and Gene Therapy Market - Industry Analysis
13.1 Drivers
Restraints
and Opportunities
13.1.1 Overview
13.1.2 Drivers
13.1.3 Restraints
13.1.4 Opportunities
13.2 Porters Five Forces Analysis
13.2.1 Overview
13.2.2 Bargaining Power of Buyers
13.2.3 Bargaining Power of Suppliers
13.2.4 Degree of Competition
13.2.5 Threat of New Entrants
13.2.6 Threat of Substitutes
13.3 Value Chain Analysis
14 Appendix
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/