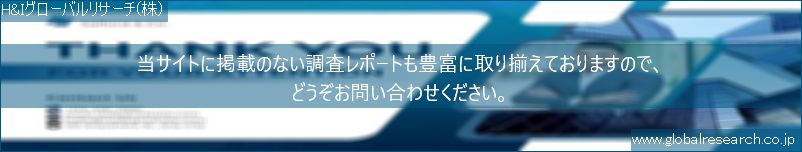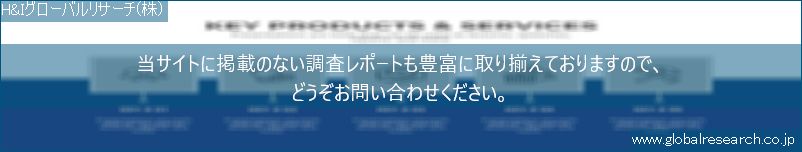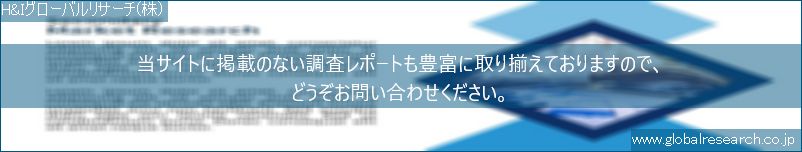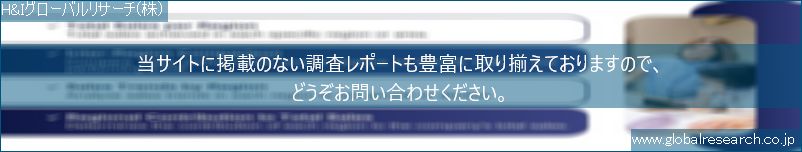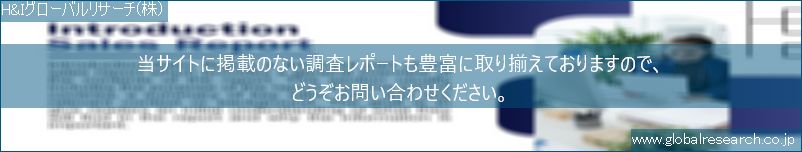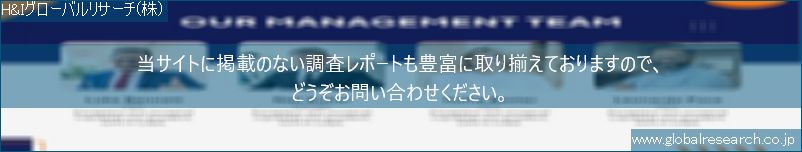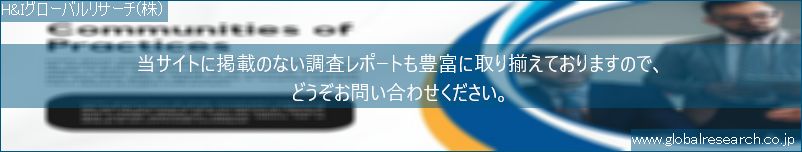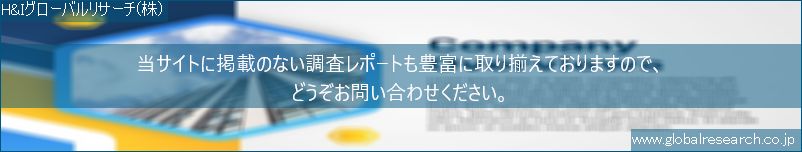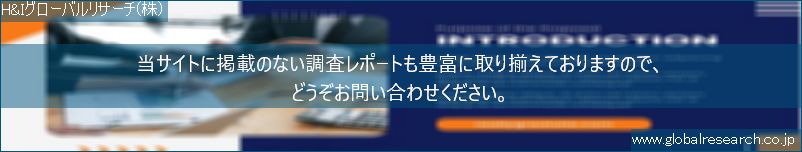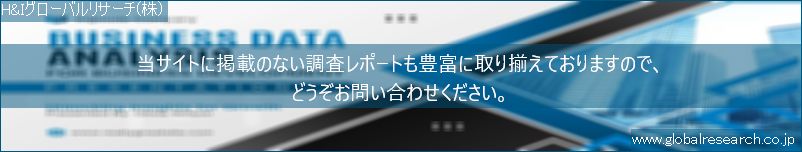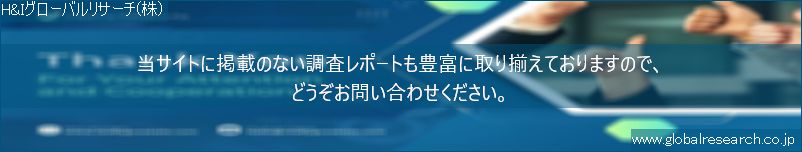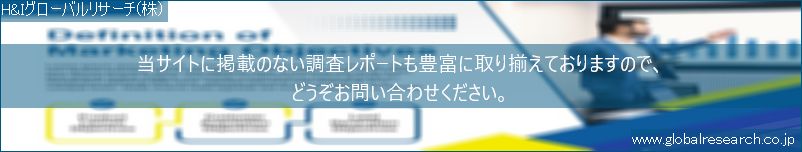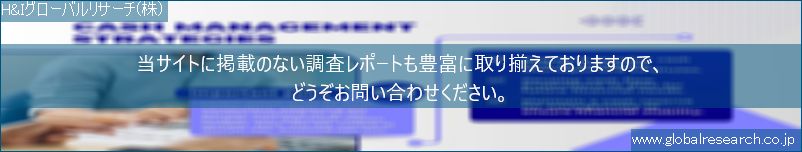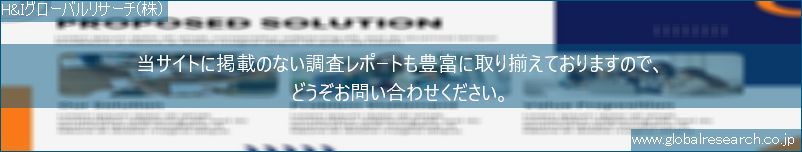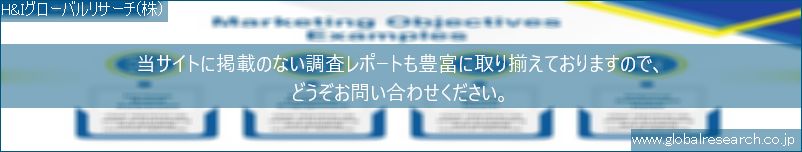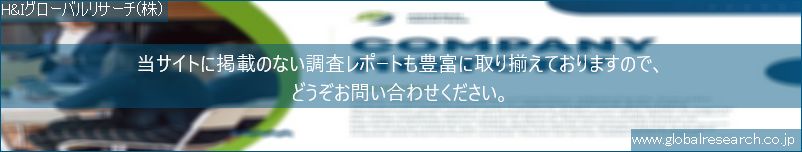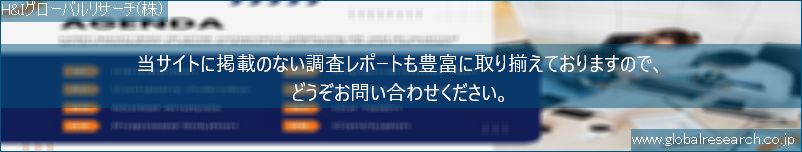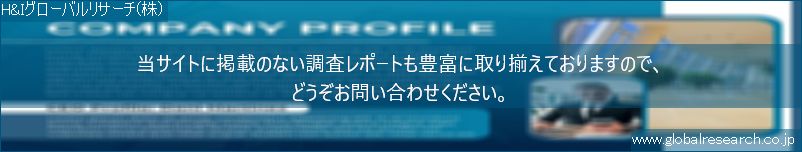日本のesports市場規模は2024年に1億3990万USDとなった。今後、IMARC Groupは、2033年には3億9,110万米ドルに達し、2025年から2033年までの年平均成長率は12.1%になると予測している。同市場は、若年層における人気の高まりや、政府の支援、業界の協力などを主な要因として、大きく拡大している。さらに、プロリーグやトーナメントの拡大、教育機関へのesportsの統合、ファン参加型ストリーミングの進化が、市場拡大にさらに貢献している。
日本の若年層におけるesports人気の高まりは、市場の主要な促進要因である。対戦型ゲームは娯楽の主流形態へと変貌を遂げ、若年層はesportsイベントのプレイと視聴の両方に積極的に参加している。例えば、2024年に日本の若者を対象に行われた調査では、18歳から39歳の40%以上が、esportsが将来のオリンピックの一部になると考えていることがわかった。特に18~29歳(43.7%)と30代(42.5%)の支持が高かった。さらに、参加者の48%がesportsを人気が出るスポーツと見ている。この傾向は、若い層の間でesportsの人気が高まっていることを浮き彫りにしており、ゲームが正当な競技種目として認知されていることを反映しています。技術やストリーミング・プラットフォームの進歩と相まって、プロトーナメントの普及が進んでいるため、esportsは主流のエンターテインメントに昇華しています。若い観客はプレイヤーとしてだけでなく、熱狂的な観客としてもesportsに積極的に参加し、視聴率と業界の成長を牽引している。オリンピックにesportsが採用される可能性は、世界的に認知されたスポーツとしてのゲームの進化した認識と一致し、日本の若者の間でesportsの文化的意義をさらに強固なものにしている。
政府の取り組みや業界の協力も、日本のesports市場を大きく後押ししている。日本政府は、賞金に関する法的規制を緩和し、観光や地域再生イニシアティブへの組み込みを推進することで、esportsを受け入れており、スポーツの潜在的な経済的・社会的利益を認めている。プロリーグの創設、大規模大会の開催、対戦ゲームのインフラ整備など、ゲーム開発者、スポンサー、イベント企画者の連携が市場の拡大をさらに促している。例えば、2024年9月、Apex Legends Championship Series(ALGS)はソニーと提携し、2025年初頭に札幌で開催されるALGS Year 4 Championshipの公式モニタープロバイダーとして同社のゲーミングブランドINZONEを採用した。ソニーのM10SモニターはFnaticと共同設計され、イベントで使用される。ALGSは現在、Alienware、Herman Miller、Battle Beaverを含む4つのパートナーを持っています。このような戦略的な取り組みにより、日本はアジアをリードするesportsのハブとして位置づけられ、国内外からesports業界への関心が高まっている。
日本のesports市場動向:
プロリーグとトーナメントの拡大
日本のesportsビジネスにおける注目すべきトレンドの1つは、プロesportsリーグと大会の急速な拡大である。League of Legends、Street Fighter、Valorantのような有名なビデオゲームは非常に人気があり、組織化されたリーグや選手権の創設に貢献している。エリートの才能を紹介するだけでなく、ライブ会場やインターネット放送サービスのおかげで、これらのイベントには多くの観客が集まる。スポンサーや広告主は、観戦スポーツとしての人気の高まりからesportsに多額の投資を行っており、この分野はさらに専門化されている。 例えば、2024年3月、日本で大きなプレゼンスを持つライオットゲームズは、スポンサーへの依存度を下げることで持続可能性を目指し、リーグ・オブ・レジェンド(LoL)Esportsのビジネスモデルを見直す計画を発表した。前年度、LoL EsportsはMSIとWorldsイベントのAMAがそれぞれ58%と65%増加し、地域リーグ全体の成長率は16%だった。この変更には、チームへの固定給、ゲーム内デジタルコンテンツからの収益分配、一般(50%)、競技(35%)、ファンダム(15%)に分けられたグローバル・レベニュー・プール(GRP)などが含まれる。スポンサーシップも2024年初頭に成長を見せ、HPやハイネケンなどのパートナーが参加した。さらに、これらのトーナメントは、日本の文化およびエンターテインメント部門にとって不可欠なものとなっており、国内外から注目を集めている。
教育とトレーニングへのエスポーツの統合
esportsが合法的なプロの道として人気を博すにつれ、日本の教育・訓練機関への導入も進んでいる。チームワーク、戦略開発、ゲーム能力を重視するEsportsプログラムは、学校や大学によって導入されている。これらのプログラムでは、業界の技術や商業的要素についても学ぶことができる。 例えば2024年、テンプル大学ジャパンキャンパス(TUJ)はアジア電子スポーツ連盟(AESF)と提携し、esportsの教育、トレーニング、大会を強化した。TUJのesportsチームは、1月20-21日と2月3-4日に開催された筑波大学のゲームイベントに出場しました。これらの取り組みは、選手、解説者、イベント主催者など、次世代のesportsプロフェッショナルを育成することを目的としています。人材育成を行うことで、日本は世界のesports分野で競争力を持つ国として位置づけられている。
ストリーミングとファン参加における進歩
日本のesports産業の未来は、ストリーミング技術とファンとの交流戦術の発展によって形作られている。Twitch、YouTube Gaming、国内サービスなどのプラットフォームを通じて、プレイヤー、ストリーマー、視聴者間のリアルタイムコミュニケーションが可能になった。ファンネットワークを強化し、視聴者体験を向上させることで、この交流はエンゲージメントとロイヤリティを高める。例えば、ストリームチャート調査によると、2024年、日本のストリームは、YouTube、Twitch、SOOPを含む10のプラットフォームにまたがって、21億7000万時間以上の視聴時間を生み出した。さらに、舞台裏ビデオやインタラクティブなライブストリームなどの革新的なコンテンツ形式は、ファンがお気に入りのチームや選手とつながる方法を再定義している。このような進歩は視聴者数を拡大するだけでなく、新たな収益源を生み出し、esportsのエコシステムにおける重要なプレーヤーとしての日本の地位を確固たるものにしている。
日本のエスポーツ産業のセグメンテーション
IMARC Groupは、日本esports市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2025年から2033年までの国・地域レベルの予測を提供しています。市場は収益モデル、プラットフォーム、ゲームに基づいて分類されています。
収益モデル別の分析
– メディアライツ
– 広告およびスポンサーシップ
– マーチャンダイズとチケット
– その他
メディアライツとは、放送局やストリーミングサービスがesportsコンテンツを発信することを許可するライセンス契約のことを指す。この収益モデルは、日本のesports業界にとって不可欠なものである。企業は有名なリーグや大会の独占放送権を得ることで、視聴者を増やし、大きな利益を得ている。プロ化を促進し、スポンサーやメディア企業から資金を集め、esportsを人気エンターテインメントの地位に押し上げることで、この戦略は市場を支援している。メディア権を通じた露出の増加は、ファンの交流も促進し、業界の拡大を加速させる。
収益モデルのセクションで、スポンサーシップと広告とは、企業や組織がesportsチーム、選手、イベントを通じて商品やサービスを宣伝するために行う金銭的貢献を指す。多額の資金を提供し、esports活動の認知度を高めるため、このアプローチは日本のesportsセクターにとって不可欠である。著名な企業はスポンサーシップに資金を費やし、関心の高い視聴者にリーチし、大会やストリーム中に広告を掲載することで、幅広いブランド認知を保証します。このWin-Winの戦略は、業界の収益を増加させながら、日本におけるesportsのプロ化と成長を促進します。
グッズやチケットの販売は、日本のesports市場におけるビジネスモデルの重要な部分であり、その拡大に大きく貢献している。ブランドの衣類、アクセサリー、グッズは商品の一例であり、ライブのesports大会やイベントはチケット販売を提供する。これらのチャネルはファンの交流を向上させ、チーム、イベント企画者、スポンサーに直接的な収入源を与えている。日本におけるesports人気の高まりは、プレミアムグッズやイベントへのアクセスに対する需要を高め、この分野に関わるすべての関係者の長期的な存続と経済的な成功を促進する盛況なエコシステムを作り出している。
プラットフォーム別分析
– PCベースのEsports
– コンソールベースのEsports
– モバイルとタブレット
PCベースのesportsは、その優れたビジュアル、適応性の高い構成、およびトップクラスのアクセサリーとの互換性から、日本のesports市場にとって不可欠なものである。プロもカジュアルゲーマーもPCベースのesportsに惹かれ、熾烈な競争の雰囲気を作り出し、スポンサーと視聴者を増やしている。プラットフォームの拡張性は、大規模な大会の開催を容易にし、esportsの世界における日本の地位を強化し、強力で収益性の高いゲーム産業の成長を促進する。
プラットフォームセグメントにおけるコンソールベースのesportsは、コンソールを使用した対戦型ゲームを含む。日本ではコンソールゲームへの親和性が高いため、このセグメントは日本のesports市場で重要な位置を占めている。コンソールが入手しやすく、日本の消費者に広く普及していることが、強固な対戦ゲーム文化の醸成に役立っている。また、コンソールベースのesportsは、トーナメント、商品、スポンサーシップを通じて収益を上げ、市場の安定成長に貢献している。
日本のesports市場におけるモバイル・タブレット分野は、携帯端末に最適化されたゲーム・プラットフォームであり、プレイヤーや視聴者にアクセシビリティと利便性を提供している。日本におけるスマートフォンやタブレットの普及に伴い、これらのプラットフォームはesportsへの参加と視聴者のエンゲージメントの要となっている。これらのプラットフォームはカジュアルゲーマーや競技プレイヤーに対応し、外出先でのシームレスなゲームプレイやライブストリーミングを可能にしている。このセグメントは、そのリーチを広げ、新しい層を引き付け、簡単にアクセスできるポータブルなゲームソリューションを通じてコミュニティの交流を促進することにより、日本のesports産業の成長を牽引している。
ゲーム別の分析
– マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ(MOBA)
– プレイヤー対プレイヤー(PvP)
– ファースト・パーソン・シューティング(FPS)
– リアルタイムストラテジー(RTS)
マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ(MOBA)ゲームは、esportsで人気のあるジャンルで、プレイヤーは戦略的な目標を達成するためにユニークなキャラクターを操作するチームベースのゲームプレイを含みます。MOBAゲームは競技性を高めるため、プロのトーナメントやリーグの定番となっている。その戦略的な奥深さとテンポの速いアクションは観客を魅了し、視聴率とスポンサーシップの機会を押し上げる。MOBAの人気は日本のesportsエコシステムを強化し、人材育成、ファン参加、全体的な市場拡大の成長を促進する。
ゲーム分野でのプレイヤー対プレイヤー(PvP)ゲームは、ゲーム環境内での個々のプレイヤーまたはチーム間の直接的な競争を伴う。この形式は日本のesports市場の要であり、PvPゲームは激しい競争とスキルベースのゲームプレイを促進し、参加者と観客の両方を魅了する。日本では、これらのゲームはローカルおよび国際的なトーナメントを通じてエンゲージメントを促進し、esportsの文化的な隆盛に貢献しています。さらに、PvPタイトルはスポンサーシップ、チケット販売、ゲーム内課金、ライブストリーミングパートナーシップを通じて収益源を生み出し、市場の拡大を支えている。
FPS(ファーストパーソン・シューティング)ゲームは、没入感のあるゲームプレイと戦略的な奥深さで知られ、日本のesports市場で重要なセグメントを形成している。FPSゲームは、魅力的なトーナメントを提供し、チームの協力を促進し、個人のスキルを披露することで、競技エコシステムを強化している。日本では、そのテンポの速いアクション主導の性質が若い観客にアピールし、視聴率とスポンサーシップの機会を促進している。このジャンルの人気は、日本のesports産業の成長を支え続け、世界的な隆盛に貢献している。
リアルタイムストラテジー(RTS)ゲームは、プレイヤーがリアルタイムで資源、ユニット、戦略を管理し、対戦相手を出し抜くゲームである。このジャンルは、迅速な意思決定と戦略的思考が要求されるため、日本のesports市場で大きな支持を得ている。RTSセグメントは、熟練プレイヤーを引き付け、トーナメントやライブストリーミングイベントを通じてファンを魅了することで、esportsの成長を促進している。RTSがesportsリーグに組み込まれることで、視聴率とスポンサーシップの機会が高まり、日本のesports産業全体の拡大に寄与している。
地域分析:
– 関東地方
– 近畿地方
– 中部地方
– 九州・沖縄地方
– 東北地方
– 中国地方
– 北海道地方
– 四国地方
関東地方は、人口密度と高度なインフラによって、日本のesports市場にとって重要な拠点となっています。東京を擁するこの地域では、数多くのesportsイベント、トーナメント、ゲーム博覧会が開催され、国内外からプレイヤーや観客が集まってくる。大手ゲーム会社、ストリーミング・プラットフォーム、esports団体がここに本社を構え、コラボレーションとイノベーションを促進している。この地域の活気あるゲーム文化、最先端の会場、利用しやすい交通機関は、esportsの推進における役割をさらに高めている。関東の影響力は、日本のesports産業の成長とプロ化に大きく貢献している。
大阪や京都などの大都市を含む近畿地方は、日本のesports市場において極めて重要な役割を果たしている。技術革新と活気ある若者文化の拠点として、この地域では数多くのesportsトーナメント、ゲーム博覧会、コミュニティイベントが開催されている。また、esports会場やトレーニングセンターなどのインフラも充実しており、人材育成や対戦型ゲームの育成にも力を入れています。大手ゲーム会社の存在と消費者の強い関心が、この地域の貢献度をさらに高めている。これらの要因から、近畿はesportsの成長の重要な原動力となっており、地域と国の両方の市場ダイナミクスを高めている。
中部地方は、インフラと人材育成を促進することで、日本のesports市場の発展に重要な役割を果たしている。技術革新と強力なゲーム文化で知られるこの地域では、プレイヤーや観客を魅了するトーナメント、トレーニング施設、esportsイベントが開催されています。地方自治体や企業は、地域の経済成長と観光を促進するためにesportsに投資している。さらに、この地域の戦略的な立地は、国内および国際的なイベントへのアクセスを高めている。中部地方は日本のesportsエコシステムにとって重要な貢献者であり、その拡大と国際競争力を促進している。
九州・沖縄地域は、その強力なインフラと成長するデジタルエコシステムを活用することで、日本のesports市場の発展に重要な役割を果たしています。この地域では、esportsのトーナメント、トレーニングセンター、イベントが開催され、プレーヤーと観客の両方を魅了しています。地方自治体の支援と民間セクターの投資は、ゲーミングハブの開発を促進し、プロゲーマーのための機会を高めています。さらに、九州・沖縄はesportsを観光とエンターテインメント分野に統合することに注力しており、日本のesports市場全体の成長と多様化に貢献しながら、地域経済をさらに後押ししている。
東北地方は、草の根的な取り組みや地域大会の拡大を通じて、日本のesports市場に貢献する重要な地域として台頭している。ゲーミングインフラへの投資の増加やコミュニティに焦点を当てたイベントにより、東北地方は地元の才能を育成し、競技ゲームへの参加を促進している。この地域の教育機関は、esportsプログラムを統合し、若年層のスキル開発を支援しています。文化的・経済的活動としてesportsを推進することで、東北は国内のesportsエコシステムにおける知名度を高め、日本の対戦ゲーム市場の多様化と拡大に貢献している。
中国地方は、成長するインフラと競技ゲームに対する地元の強い関心を活用し、日本のesports市場で影響力のあるプレーヤーとして台頭している。広島などの主要都市は、地域大会の開催、草の根参加者の育成、スポンサー誘致の拠点となっています。この地域の大学や教育機関は、esportsプログラムをますます統合し、若い才能を育成し、認知度を高めています。さらに、Chugokuはコミュニティベースのゲームイベントに重点を置いており、参加と包括性を促進しています。これらの努力は、日本におけるesportsエコシステムの拡大を総合的にサポートし、日本全体の成長に貢献しています。
北海道は、そのユニークな文化と地理的な魅力を活かしてプレイヤーと観客を惹きつけ、日本のesports市場に貢献する存在として台頭しつつある。この地域では、esportsトーナメントやゲームイベントの開催が増加しており、地域社会との関わりや観光を促進している。地元のイニシアティブは、人材育成を支援し、意欲的なゲーマーに機会を提供し、esports教育を推進しています。独特の魅力と没入型体験の創出に重点を置く北海道は、日本のesportsエコシステムの多様性を高め、市場の拡大に貢献し、より広範なゲーム業界における地位を強化しています。
四国地方は、ゲーム文化の振興と人材育成を目的とした取り組みを通じて、日本のesports市場に貢献する地域として台頭しつつある。地方自治体や企業は、esports施設、トレーニングプログラム、コミュニティイベントに投資し、愛好家の参加とプロプレイヤーの育成を図っている。地域トーナメントを開催したり、教育やレクリエーションプログラムにesportsを組み込んだりすることで、四国は若いプレイヤーに機会を創出し、スポンサーを誘致している。このような取り組みは、地域経済を活性化させるだけでなく、拡大する日本のesports産業における四国の地位を強化している。
競争環境:
市場の競争環境は、ゲームパブリッシャー、テクノロジープロバイダー、イベント主催者間の激しい競争によって特徴付けられる。著名なプレーヤーには、イノベーションとスポンサーシップを推進する大手ゲーム会社が含まれる。例えば、2024年10月、コナミは『幻想水滸伝I&II HDリマスター』、『メタルギアソリッドデルタ』、『スネークイーター』、『遊戯王デルタ』など6タイトルの世界同時発売を決定した:スネークイーター」、「遊☆戯☆王アーリーデイズコレクション」、「サイレントヒル」2タイトルを含む。さらに、新興のスタートアップ企業や地方組織も、大会運営や選手育成のニッチを開拓している。グローバルなesportsブランドとのコラボレーションは、競争環境をさらに激化させ、インフラ、観客動員、収益化戦略の進歩を促進している。
本レポートでは、日本esports市場の競争環境を包括的に分析し、主要企業の詳細なプロフィールを掲載しています。
最新ニュースと動向:
– 2024年、PUBGモバイルとUndawnのクリエイターであるLightSpeed Studiosは、カプコンのレジェンドである伊津野英昭氏が率いる日本を拠点とする新しい開発スタジオを立ち上げました。東京と大阪に拠点を置き、AAAゲームの開発に注力するが、具体的なプロジェクトの詳細は未発表。
– 2024年6月、日本エスポーツ連合は日本オリンピック委員会に準会員として加盟し、2027年3月31日まで日本代表として国際的なesports大会に参加できるようになった。esportsへの参加者が増える中、ゲームのプロから実践的な技術や知識を学ぶ学校も設立されており、esportsの注目度が高まっていることがうかがえる。
本レポートで扱う主な質問
– 1.esportsとは何か?
– 2.日本のesports市場の規模は?
– 3.2025-2033年の日本esports市場の予想成長率は?
– 4.日本のesports市場を牽引する主要因は何か?
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Japan Esports Market - Introduction
4.1 Overview
4.2 Market Dynamics
4.3 Industry Trends
4.4 Competitive Intelligence
5 Japan Esports Market Landscape
5.1 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
5.2 Market Forecast (2025-2033)
6 Japan Esports Market - Breakup by Revenue Model
6.1 Media Rights
6.1.1 Overview
6.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.1.3 Market Forecast (2025-2033)
6.2 Advertising and Sponsorships
6.2.1 Overview
6.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.2.3 Market Forecast (2025-2033)
6.3 Merchandise and Tickets
6.3.1 Overview
6.3.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.3.3 Market Forecast (2025-2033)
6.4 Others
6.4.1 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.4.2 Market Forecast (2025-2033)
7 Japan Esports Market - Breakup by Platform
7.1 PC-based Esports
7.1.1 Overview
7.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.1.3 Market Forecast (2025-2033)
7.2 Consoles-based Esports
7.2.1 Overview
7.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.2.3 Market Forecast (2025-2033)
7.3 Mobile and Tablets
7.3.1 Overview
7.3.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.3.3 Market Forecast (2025-2033)
8 Japan Esports Market - Breakup by Games
8.1 Multiplayer Online Battle Arena (MOBA)
8.1.1 Overview
8.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.1.3 Market Forecast (2025-2033)
8.2 Player vs Players (PvP)
8.2.1 Overview
8.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.2.3 Market Forecast (2025-2033)
8.3 First Person Shooters (FPS)
8.3.1 Overview
8.3.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.3.3 Market Forecast (2025-2033)
8.4 Real Time Strategy (RTS)
8.4.1 Overview
8.4.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.4.3 Market Forecast (2025-2033)
9 Japan Esports Market – Breakup by Region
9.1 Kanto Region
9.1.1 Overview
9.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.1.3 Market Breakup by Revenue Model
9.1.4 Market Breakup by Platform
9.1.5 Market Breakup by Games
9.1.6 Key Players
9.1.7 Market Forecast (2025-2033)
9.2 Kinki Region
9.2.1 Overview
9.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.2.3 Market Breakup by Revenue Model
9.2.4 Market Breakup by Platform
9.2.5 Market Breakup by Games
9.2.6 Key Players
9.2.7 Market Forecast (2025-2033)
9.3 Central/ Chubu Region
9.3.1 Overview
9.3.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.3.3 Market Breakup by Revenue Model
9.3.4 Market Breakup by Platform
9.3.5 Market Breakup by Games
9.3.6 Key Players
9.3.7 Market Forecast (2025-2033)
9.4 Kyushu-Okinawa Region
9.4.1 Overview
9.4.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.4.3 Market Breakup by Revenue Model
9.4.4 Market Breakup by Platform
9.4.5 Market Breakup by Games
9.4.6 Key Players
9.4.7 Market Forecast (2025-2033)
9.5 Tohoku Region
9.5.1 Overview
9.5.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.5.3 Market Breakup by Revenue Model
9.5.4 Market Breakup by Platform
9.5.5 Market Breakup by Games
9.5.6 Key Players
9.5.7 Market Forecast (2025-2033)
9.6 Chugoku Region
9.6.1 Overview
9.6.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.6.3 Market Breakup by Revenue Model
9.6.4 Market Breakup by Platform
9.6.5 Market Breakup by Games
9.6.6 Key Players
9.6.7 Market Forecast (2025-2033)
9.7 Hokkaido Region
9.7.1 Overview
9.7.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.7.3 Market Breakup by Revenue Model
9.7.4 Market Breakup by Platform
9.7.5 Market Breakup by Games
9.7.6 Key Players
9.7.7 Market Forecast (2025-2033)
9.8 Shikoku Region
9.8.1 Overview
9.8.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
9.8.3 Market Breakup by Revenue Model
9.8.4 Market Breakup by Platform
9.8.5 Market Breakup by Games
9.8.6 Key Players
9.8.7 Market Forecast (2025-2033)
10 Japan Esports Market – Competitive Landscape
10.1 Overview
10.2 Market Structure
10.3 Market Player Positioning
10.4 Top Winning Strategies
10.5 Competitive Dashboard
10.6 Company Evaluation Quadrant
11 Profiles of Key Players
11.1 Company A
11.1.1 Business Overview
11.1.2 Services Offered
11.1.3 Business Strategies
11.1.4 SWOT Analysis
11.1.5 Major News and Events
11.2 Company B
11.2.1 Business Overview
11.2.2 Services Offered
11.2.3 Business Strategies
11.2.4 SWOT Analysis
11.2.5 Major News and Events
11.3 Company C
11.3.1 Business Overview
11.3.2 Services Offered
11.3.3 Business Strategies
11.3.4 SWOT Analysis
11.3.5 Major News and Events
11.4 Company D
11.4.1 Business Overview
11.4.2 Services Offered
11.4.3 Business Strategies
11.4.4 SWOT Analysis
11.4.5 Major News and Events
11.5 Company E
11.5.1 Business Overview
11.5.2 Services Offered
11.5.3 Business Strategies
11.5.4 SWOT Analysis
11.5.5 Major News and Events
12 Japan Esports Market - Industry Analysis
12.1 Drivers
Restraints
and Opportunities
12.1.1 Overview
12.1.2 Drivers
12.1.3 Restraints
12.1.4 Opportunities
12.2 Porters Five Forces Analysis
12.2.1 Overview
12.2.2 Bargaining Power of Buyers
12.2.3 Bargaining Power of Suppliers
12.2.4 Degree of Competition
12.2.5 Threat of New Entrants
12.2.6 Threat of Substitutes
12.3 Value Chain Analysis
13 Appendix
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/