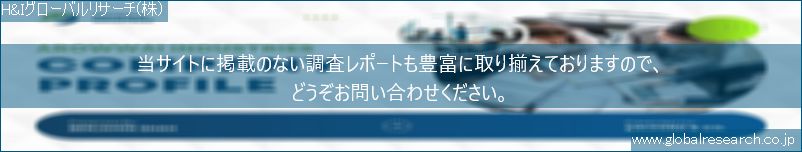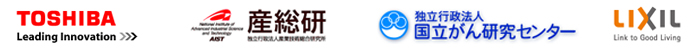1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の乗車支援システムのタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
死角検知(BSD)、車線変更支援(LCA)、後部衝突警報(RCW)、アダプティブクルーズコントロール(ACC)、前方衝突警報(FCW)
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の乗車支援システムの用途別消費額:2019年対2023年対2030年
スタンダードバイク、クルーザーバイク、トラベルバイク、スポーツバイク、モトクロス、その他
1.5 世界の乗車支援システム市場規模と予測
1.5.1 世界の乗車支援システム消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の乗車支援システム販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の乗車支援システムの平均価格(2019年-2030年)
2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Bosch、 BMW、 Continental Engineering Services Ltd.、 Rider Dome、 Ride Vision、 Honda Motor、 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.、 iRider、 Eurotech、 Yamaha、 Qianjiang Motorcycle
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの乗車支援システム製品およびサービス
Company Aの乗車支援システムの販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの乗車支援システム製品およびサービス
Company Bの乗車支援システムの販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報
…
…
3 競争環境:メーカー別乗車支援システム市場分析
3.1 世界の乗車支援システムのメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の乗車支援システムのメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の乗車支援システムのメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 乗車支援システムのメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における乗車支援システムメーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における乗車支援システムメーカー上位6社の市場シェア
3.5 乗車支援システム市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 乗車支援システム市場:地域別フットプリント
3.5.2 乗車支援システム市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 乗車支援システム市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携
4 地域別消費分析
4.1 世界の乗車支援システムの地域別市場規模
4.1.1 地域別乗車支援システム販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 乗車支援システムの地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 乗車支援システムの地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の乗車支援システムの消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の乗車支援システムの消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の乗車支援システムの消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の乗車支援システムの消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの乗車支援システムの消費額(2019年-2030年)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の乗車支援システムのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の乗車支援システムのタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の乗車支援システムのタイプ別平均価格(2019年-2030年)
6 用途別市場セグメント
6.1 世界の乗車支援システムの用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の乗車支援システムの用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の乗車支援システムの用途別平均価格(2019年-2030年)
7 北米市場
7.1 北米の乗車支援システムのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の乗車支援システムの用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の乗車支援システムの国別市場規模
7.3.1 北米の乗車支援システムの国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の乗車支援システムの国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)
8 欧州市場
8.1 欧州の乗車支援システムのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の乗車支援システムの用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の乗車支援システムの国別市場規模
8.3.1 欧州の乗車支援システムの国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の乗車支援システムの国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の乗車支援システムのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の乗車支援システムの用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の乗車支援システムの地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の乗車支援システムの地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の乗車支援システムの地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
10 南米市場
10.1 南米の乗車支援システムのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の乗車支援システムの用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の乗車支援システムの国別市場規模
10.3.1 南米の乗車支援システムの国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の乗車支援システムの国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)
11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの乗車支援システムのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの乗車支援システムの用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの乗車支援システムの国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの乗車支援システムの国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの乗車支援システムの国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
12 市場ダイナミクス
12.1 乗車支援システムの市場促進要因
12.2 乗車支援システムの市場抑制要因
12.3 乗車支援システムの動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係
13 原材料と産業チェーン
13.1 乗車支援システムの原材料と主要メーカー
13.2 乗車支援システムの製造コスト比率
13.3 乗車支援システムの製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 乗車支援システムの主な流通業者
14.3 乗車支援システムの主な顧客
15 調査結果と結論
16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項
・世界の乗車支援システムのタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の乗車支援システムの用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の乗車支援システムのメーカー別販売数量
・世界の乗車支援システムのメーカー別売上高
・世界の乗車支援システムのメーカー別平均価格
・乗車支援システムにおけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と乗車支援システムの生産拠点
・乗車支援システム市場:各社の製品タイプフットプリント
・乗車支援システム市場:各社の製品用途フットプリント
・乗車支援システム市場の新規参入企業と参入障壁
・乗車支援システムの合併、買収、契約、提携
・乗車支援システムの地域別販売量(2019-2030)
・乗車支援システムの地域別消費額(2019-2030)
・乗車支援システムの地域別平均価格(2019-2030)
・世界の乗車支援システムのタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の乗車支援システムのタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の乗車支援システムのタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の乗車支援システムの用途別販売量(2019-2030)
・世界の乗車支援システムの用途別消費額(2019-2030)
・世界の乗車支援システムの用途別平均価格(2019-2030)
・北米の乗車支援システムのタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の乗車支援システムの用途別販売量(2019-2030)
・北米の乗車支援システムの国別販売量(2019-2030)
・北米の乗車支援システムの国別消費額(2019-2030)
・欧州の乗車支援システムのタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の乗車支援システムの用途別販売量(2019-2030)
・欧州の乗車支援システムの国別販売量(2019-2030)
・欧州の乗車支援システムの国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の乗車支援システムのタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の乗車支援システムの用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の乗車支援システムの国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の乗車支援システムの国別消費額(2019-2030)
・南米の乗車支援システムのタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の乗車支援システムの用途別販売量(2019-2030)
・南米の乗車支援システムの国別販売量(2019-2030)
・南米の乗車支援システムの国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの乗車支援システムのタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの乗車支援システムの用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの乗車支援システムの国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの乗車支援システムの国別消費額(2019-2030)
・乗車支援システムの原材料
・乗車支援システム原材料の主要メーカー
・乗車支援システムの主な販売業者
・乗車支援システムの主な顧客
*** 図一覧 ***
・乗車支援システムの写真
・グローバル乗車支援システムのタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル乗車支援システムのタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル乗車支援システムの用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル乗車支援システムの用途別売上シェア、2023年
・グローバルの乗車支援システムの消費額(百万米ドル)
・グローバル乗車支援システムの消費額と予測
・グローバル乗車支援システムの販売量
・グローバル乗車支援システムの価格推移
・グローバル乗車支援システムのメーカー別シェア、2023年
・乗車支援システムメーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・乗車支援システムメーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル乗車支援システムの地域別市場シェア
・北米の乗車支援システムの消費額
・欧州の乗車支援システムの消費額
・アジア太平洋の乗車支援システムの消費額
・南米の乗車支援システムの消費額
・中東・アフリカの乗車支援システムの消費額
・グローバル乗車支援システムのタイプ別市場シェア
・グローバル乗車支援システムのタイプ別平均価格
・グローバル乗車支援システムの用途別市場シェア
・グローバル乗車支援システムの用途別平均価格
・米国の乗車支援システムの消費額
・カナダの乗車支援システムの消費額
・メキシコの乗車支援システムの消費額
・ドイツの乗車支援システムの消費額
・フランスの乗車支援システムの消費額
・イギリスの乗車支援システムの消費額
・ロシアの乗車支援システムの消費額
・イタリアの乗車支援システムの消費額
・中国の乗車支援システムの消費額
・日本の乗車支援システムの消費額
・韓国の乗車支援システムの消費額
・インドの乗車支援システムの消費額
・東南アジアの乗車支援システムの消費額
・オーストラリアの乗車支援システムの消費額
・ブラジルの乗車支援システムの消費額
・アルゼンチンの乗車支援システムの消費額
・トルコの乗車支援システムの消費額
・エジプトの乗車支援システムの消費額
・サウジアラビアの乗車支援システムの消費額
・南アフリカの乗車支援システムの消費額
・乗車支援システム市場の促進要因
・乗車支援システム市場の阻害要因
・乗車支援システム市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・乗車支援システムの製造コスト構造分析
・乗車支援システムの製造工程分析
・乗車支援システムの産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
| ※参考情報 乗車支援システム(Riding Assistance System)は、主に運転者と乗客の安全性、快適性、効率性を向上させるために設計された先進的な技術の集合体です。このシステムは、自動車や二輪車などの乗り物に搭載され、運転時の負担を軽減し、交通事故のリスクを低減させることを目的としています。乗車支援システムは、さまざまな技術を用いることで、運転者や乗客にとっての最適な乗車体験を提供します。 まず、乗車支援システムの定義についてですが、これは自動車、自転車、或いはオートバイなど、様々な形態の乗り物において運転者を支援するための技術や機能を指します。具体的には、車両の運行に関する情報提供や警告、安全機能、運転支援機能、乗客の快適さを向上させるための多様な機能が含まれます。 次に、乗車支援システムの特徴について考えてみましょう。このシステムの代表的な特徴には、自動運転技術、事故防止機能、運転者の疲労軽減機能、ナビゲーション支援、運転効率化のための情報提供などがあります。自動運転技術は、センサーやカメラを用いて周囲の環境を認識し、車両の制御を自動的に行うものです。これによって、運転者の負担を大幅に軽減することが可能となります。 また、事故防止機能としては、自動ブレーキ、車両衝突警告、車線逸脱警告などが挙げられます。これらは、運転者が気づいていない危険を検知し、事前に警告や自動操作を行うことで、事故発生のリスクを減少させます。さらに、運転者の疲労軽減を目的とする機能としては、自動定速走行装置(クルーズコントロール)や、運転中の状態をモニタリングし疲労を知らせるドライバー監視システムなどがあります。 乗車支援システムには、いくつかの種類が存在します。それぞれの乗り物の特性や目的に応じて使用されるため、その種類は多岐にわたります。自動車に搭載される場合、主に以下のようなシステムに分けられます。運転支援システム、自動運転システム、緊急ブレーキ支援システム、衝突回避支援システム、車線維持支援システムなどです。これらのシステムは、運転のスタイルや条件に応じて組み合わせて使用されることが一般的です。 乗車支援システムの用途として、日常的な運転支援から、特定の条件下での使用まで多様な場面が考えられます。特に都市部においては、交通量が多く、歩行者や自転車との接触リスクが高まるため、システムの役割は重要になります。また、高速道路においては、長距離運転による疲労や集中力の低下を防ぐために、クルーズコントロールや自動運転機能が有効です。これにより、運転者は長時間の運転でも快適に移動することができます。 さらに関連技術についても触れておきましょう。近年の乗車支援システムは、人工知能(AI)、機械学習、ビッグデータ、IoT(モノのインターネット)などの進展によって、その進化が加速しています。AIを用いることで、運転者の行動を学習し、より的確なサポートが可能となります。また、IoT技術を活用することで、車両同士の通信や外部環境との情報共有が促進され、リアルタイムでの状況判断が行えるようになります。このような技術的な進化は、将来的により高度な自動運転社会の実現に向けた一歩となるでしょう。 さらに、乗車支援システムには、ユーザーインターフェースの重要性も見逃せません。運転者や乗客にとって使いやすい操作性や視覚的なフィードバックは、安心感を生む要因となります。特に視覚的な警告表示や音声案内は、運転中の注意を引きやすく、即座に反応しやすいといったメリットがあります。運転者がシステムに対して信頼を持つためには、こうしたインターフェースの設計が欠かせません。 乗車支援システムの導入により、さまざまな利点が得られます。運転者はストレスを軽減し、快適な移動が可能になります。また、交通事故を減少させることで、自動車事故による社会的なコストも削減される期待があります。そして、環境への配慮として、運転効率が向上することで、燃料消費量の低下やCO2排出量の削減にもつながります。 今後の展望としては、乗車支援システムのさらなる進化が期待されています。より高度な自動運転技術の普及により、人々の移動の仕方が根本的に変わる可能性があります。また、スマートシティやモビリティサービスの発展とともに、乗車支援システムは重要な役割を果たすことが求められるでしょう。特に高齢化社会においては、運転支援技術が高齢者や運転が困難な方々の移動をサポートするための鍵となるはずです。 総じて、乗車支援システムは、現代の交通社会において欠かすことのできない技術であり、今後もその発展が期待される分野です。運転者と乗客の安全性や快適性を向上させるその役割は、ますます重要になってくるでしょう。そのため、技術の進展に伴い、新たな機能やサービスの開発が進められ、より良い移動体験が提供されることに期待が寄せられています。これは、私たちの生活の質を高め、安心して移動できる社会を実現するための重要なステップであると言えるでしょう。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/