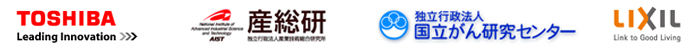2025年10月27日
H&Iグローバルリサーチ(株)
*****「作物収穫ロボットのグローバル市場(2025年~2029年):製品別(果物・野菜収穫ロボット、穀物収穫ロボット)」産業調査レポートを販売開始 *****
H&Iグローバルリサーチ株式会社(本社:東京都中央区)は、この度、Technavio社が調査・発行した「作物収穫ロボットのグローバル市場(2025年~2029年):製品別(果物・野菜収穫ロボット、穀物収穫ロボット)」市場調査レポートの販売を開始しました。作物収穫ロボットの世界市場規模、市場動向、市場予測、関連企業情報などが含まれています。
***** 調査レポートの概要 *****
- 市場定義と適用範囲
作物収穫ロボットは、露地・施設園芸・果樹園などで、熟度判定・位置特定・収穫動作・搬送を部分的または完全に自動化する機械システムである。構成要素は、(a)移動プラットフォーム(自律台車、レール、クローラ、牽引型)、(b)センシング(RGB/深度カメラ、近赤外、ハイパースペクトル、LiDAR)、(c)熟度・果実検出AI、(d)エンドエフェクタ(ソフトグリッパ、吸着、剪果機構)、(e)アーム(多関節/SCARA/直交)、(f)収穫物の一次選別・搬送、(g)フリート管理・クラウド最適化で構成される。対象作物は果実類(いちご、トマト、リンゴ、柑橘)、果菜類(キュウリ、パプリカ)、一部穀物・根菜(収穫支援)、葉菜の剪葉などに及ぶ。
- マーケットドライバー:なぜ今、収穫ロボットか
主因は(1)慢性的な人手不足と高齢化、(2)賃金上昇や季節労働者の確保難、(3)需要予測の高度化に伴う収穫タイミング精緻化、(4)収穫後ロス削減・品質均質化、(5)施設園芸の高度化・周年栽培の拡大、(6)耐候性向上と作業安全の要請、である。さらに、センシング価格の下落とオンデバイスAIの性能向上により、収穫物の位置・熟度・遮蔽状況をリアルタイム判断できるようになり、商用化のハードルが下がっている。
- 市場規模感と成長モメンタム
「完全自動収穫」はまだ浸透初期だが、部分自動(人とロボの協調)は実装事例が増加。施設園芸面積の拡大、垂直農法・スマート農業投資、食のトレーサビリティ強化、サステナブル調達方針などが中期的な追い風。価格帯は作物・構成によって大きく振れるが、TCO(機器償却+保守+消耗品+アップデート)で労働代替と品質改善を同時に成立させる事例が増えており、“収穫量×品質×労務削減”の三面最適が投資判断の軸となっている。
- セグメンテーション①:作物別の適合性
- 果実系(いちご・トマト・パプリカ):果房構造・樹勢管理が比較的コントロールしやすく、施設内での照明・配列が標準化しやすい。熟度判別の教師データが蓄積しやすく、商用機の先行領域。
- 果樹(リンゴ・柑橘・キウイ等):樹形・枝葉の遮蔽と凹凸地形が課題。機械アームの到達性と把持・剪果の安定性が鍵で、収穫支援(振動・プラットフォーム移動の自動化)から段階導入が進む。
- 果菜・瓜類(キュウリ、ズッキーニ等):果実の摂理的成長スピードと日周変動を加味した巡回頻度が重要。ソフトグリップと切断面保護の最適化がポイント。
- 葉菜・ハーブ:“刈り取り+選別”の自動化余地が大きいが、規格・外観要求が高く、視覚検査の厳密さと搬送ラインの二次損傷低減が勝負どころ。
- 穀物・根菜:従来の収穫機械が成熟しているため、完全自動というより“視覚×最適経路”の高度化や自動追従・自律運転の付加で価値を出す領域。
- セグメンテーション②:技術アーキテクチャ
- センシング:RGB-Dと近赤外の併用で成熟度・糖度近似・表面欠陥を推定。可視光のみでは遮蔽・照度変動に弱く、補助照明や偏光で改善。
- 推論:熟度分類・物体検出・3D位置推定・把持点推定をマルチタスクで処理。モデル軽量化+オンデバイス化(Edge TPU/GPU)で遅延を抑制。
- マニピュレーション:ソフトロボティクス、吸着、剪果、ツイストなどのハイブリッド化。**“取りこぼし率”と“損傷率”**をKPIに設計。
- 移動:狭小ベンチ間の走行安定、段差・勾配対応、UWB/QR/LiDAR SLAMによる位置推定。
- システム統合:フリート管理、タスク割当、圃場デジタルツイン、ERP・受発注との連携による“収穫→出荷”のリードタイム短縮。
- ユースケースと導入モデル
(a)夜間収穫での人手置換、(b)ピークタイムの人員補完、(c)収穫+一次選別、(d)収穫予測の精緻化(面積×着果数×熟度進行)、(e)障害者雇用・多様な働き方支援との組合せ、など複線的な価値がある。導入モデルは売切り+保守、月額リース、**収穫量連動の成果課金(XaaS)**まで多様化。
- 経済性:TCOとROIの考え方
経済性は、(i)労務削減(時間×賃金×確保難リスク)、(ii)収穫タイミング適合による可販果率の上昇、(iii)収穫後ロス・損傷の低減、(iv)夜間稼働での生産計画安定化、の四本柱で評価する。初期費用はセンサー・アーム・シャシーで大きく左右されるが、フリート運用で学習データを蓄積し、シーズン更新で精度を漸進的に引き上げることで、年次のROIが改善していく。
- 地域別の導入特性
- アジア太平洋:施設園芸密度が高く、いちご・トマトのライン収穫がけん引。労働力逼迫と輸出品質基準の両立ニーズが大きい。
- 欧州:温室産地の集積、環境認証・トレーサビリティ要件の厳格化でデータ一体型収穫が進む。
- 北米:大規模化・機械化が進み、プラットフォーム型の**複合自動化(収穫+運搬+選別)**の採用余地が広い。
- 中南米・中東アフリカ:価格弾力性が高く、**段階導入(支援→半自動→全自動)**が普及シナリオ。
- 法規制・安全・倫理
人とロボが近接するため、PL(製造物責任)・機械安全・非常停止・フェールセーフは必須。収穫データの所有権・二次利用、映像データのプライバシー、アルゴリズムのバイアス(色・形状差)など、ガバナンスも求められる。輸出入では電波・電池・安全規格の適合が導入のボトルネックになりやすい。
- 競争環境とプレイヤー類型
(1)フルスタック(センサ→アーム→シャシー→SaaS)型、(2)エンドエフェクタ特化、(3)視覚AI・熟度推定特化、(4)プラットフォーム(搬送・自律台車)特化、(5)システムインテグレータ、のエコシステムで構成。優位は作物特化の現場知見×継続学習の蓄積で決まる。参入障壁は「精度の再現性」「日照・枝葉・果房変動への頑健性」「清掃・メンテ容易性」。
- 技術的ハードルとブレークスルー
課題は(a)遮蔽・重なり果、(b)光条件(逆光・低照度・結露)、(c)果柄の個体差、(d)枝葉の撓みと反力、(e)迷路状動線での到達性、(f)収穫面の微細損傷。ブレークスルーはマルチモーダル(視覚+触覚+力制御)、学習データの領域適応、自動姿勢補正、刃・吸着部のクイックメンテ、協働安全の動的ゾーニングに集中。
- データ価値と需給連動
収穫ロボットは“収穫点”の時系列データ(熟度分布、取りこぼし、収穫時刻、環境条件)を生成する。これを需要予測・ダイナミックプライシング・出荷計画・労務計画に結び、**“作る→獲る→売る”**の同期化を実現すると、価格下振れや廃棄ロスを抑制できる。標準API・データモデルの整備は普及加速の鍵。
- ビジネスモデルの進化
ハード売切りからサブスク+アップデートへ。シーズン開始時の“作物・品種モデル”を配信し、週次で微調整するML-Ops for Farmが一般化。保守は予防交換と遠隔診断が標準化し、消耗品(刃、吸着パッド、ベルト)の定額化でダウンタイムを最小化。**成果連動(取りこぼし率・損傷率のSLA)**を契約に組み込む事例が拡大。
- 価格レンジと導入の壁
導入障壁は初期費用と圃場の標準化コスト。ベンチ幅・樹形・照明・誘引といった“ロボット前提の作型”に最適化するほど、精度は上がり費用は下がる。逆に既存施設に合わせるレトロフィットは短期導入しやすいが、最大性能を発揮しにくい。小規模農家向けの共同利用(シェア)や農協・企業農場の団体契約が普及のカギ。
- 成功指標(KPI)設計
KPIは、(1)収穫速度(個/分、房/分、kg/時)、(2)取りこぼし率、(3)損傷率(微傷・圧痕・切断面品質)、(4)可販果率、(5)稼働率、(6)MTTR/MTBF、(7)夜間稼働比率、(8)シーズン中の学習改善量、(9)一人当たり取扱面積、(10)TCO/単位重量、を標準とし、作物・販路に応じて重み付けする。
- 導入プロセス:PoC→スケール
Step1:適合作物・圃場診断(樹形・遮蔽率・照明・動線)
Step2:パイロット(限定ハウスでKPI計測、基準値設定)
Step3:運用設計(夜間シフト・補助照明・搬送ライン接続・衛生動線)
Step4:スケール(フリート化、交換部品在庫、SaaS監視、教育)
Step5:継続改善(週次のモデル更新、刃・パッドの寿命管理、故障モード解析)
- サステナビリティと労働の質
ロボットは重筋作業・単純反復を肩代わりし、作業者は監督・選果・品質判断などの高付加価値工程に移る。夜間稼働の活用で昼間の人的負担を下げ、熱中症・腰痛・手指障害のリスクを軽減。収穫タイミングが均一化されることで、農薬・肥培管理の計画性も高まる。
- リスクマネジメント
主要リスクは、(a)不作・価格下落での稼働率低下、(b)部材供給・保守遅延、(c)モデル劣化(ドメインシフト)、(d)保険・補助金の適用外。対応:成果連動・リース、複数作物対応のマルチヘッド、予備機・共用プール、データの継続学習枠、現地パートナー網の構築。
- 今後5年のロードマップ
短期(~2年):いちご・トマトの収穫+選別の精度安定、夜間稼働比率の拡大。
中期(3~5年):果樹園での半自動→自動の転換点、樹形設計とロボの共同最適化、マルチモーダル把持の実装。
長期(5年以降):フリート協調と“収穫→出荷”の自律パイプライン、需要価格連動の自動収穫計画、資材・雇用計画との統合。
- まとめ:収穫点データが収益を変える
作物収穫ロボットの本質的な価値は、“人手の代替”に留まらない。いつ・どこで・どれを・どう採ったかのデータが、**売上(可販果率)×コスト(労務・ロス)**を構造的に押し上げる。現場最適の設計と継続学習の運用力を備えたプレイヤーが、作物別・地域別の“勝ちパターン”を先に確立していく。
***** 調査レポートの目次(一部抜粋) *****
1 エグゼクティブサマリー
1.1 調査目的とレポート概要
1.2 対象市場と定義(作物収穫ロボットの範囲)
1.3 基準年・予測期間・地域区分
1.4 世界市場の主要数値ハイライト(市場規模・成長率・地域別寄与)
1.5 主要成長ドライバーと機会
1.6 主要抑制要因とリスク
1.7 セグメント別ハイライト(作物別/技術別/用途別)
1.8 戦略的示唆と投資観点
2 市場定義・スコープ・調査手法
2.1 市場定義(ロボット、システム、サービスの対象範囲)
2.2 セグメンテーション(作物種別、技術アーキテクチャ、用途、地域)
2.3 調査設計(一次・二次データ、インタビュー、推計モデル)
2.4 前提条件と仮定(為替レート、価格帯、寿命、稼働率)
2.5 除外範囲と制約事項
3 マクロ環境分析
3.1 世界の農業構造・収穫労働力の動向
3.2 都市化・食料安全保障・ロジスティクスの変化
3.3 スマート農業・精密農業の展開状況
3.4 政策・補助金・投資環境(国別・地域別)
3.5 作物生産量・施設園芸面積・収穫量トレンド
3.6 技術進歩(AI、センシング、ロボット工学)
3.7 地域別市場特性と導入障壁
4 市場サイジング・成長予測
4.1 過去実績(2018–2023年)市場規模分析
4.2 基準年(2024年)市場規模
4.3 予測期間(2025–2031年または2032年)市場規模・CAGR・増分成長額
4.4 数量ベース/金額ベースの比較
4.5 価格変動・製品ミックス・技術進歩の影響分析
4.6 シナリオ別予測(ベース・楽観・保守)
4.7 地域別/セグメント別成長寄与分析
5 作物種別セグメンテーション
5.1 果実類(いちご、トマト、パプリカ、ベリー類等)
5.1.1 定義と特性
5.1.2 市場規模・成長率・地域別展開
5.2 果樹類(リンゴ、柑橘、キウイ等)
5.2.1 ユースケース・導入課題
5.2.2 市場規模・成長見通し
5.3 果菜・野菜類(キュウリ、ズッキーニ等)
5.4 葉菜・ハーブ類
5.5 穀物・根菜(補助用途)
5.6 作物別比較:収穫タイミング・熟度・遮蔽状況・仕立て条件
5.7 作物別導入ステージ(支援型→半自動→全自動)
6 技術・構成アーキテクチャ別分析
6.1 センシング技術(RGB、深度、近赤外、LiDAR、ハイパースペクトル)
6.2 AI・ソフトウェア(熟度判定、果実検出、遮蔽補正、移動経路計画)
6.3 マニピュレーション(ソフトグリッパ、吸着、剪断、ツイスト)
6.4 移動プラットフォーム(自律台車、クローラ、牽引型、レール)
6.5 システム統合・クラウド連携・フリート管理
6.6 保守・サービス(交換部品、リモート監視、データ分析)
6.7 技術別市場規模・成長・導入障壁
7 用途・導入形態別セグメンテーション
7.1 施設園芸(ハウス・棚栽培・垂直農法)
7.2 露地栽培(平地果実、果樹園)
7.3 オンサイト・小規模農場/中規模農場/企業農場別導入モデル
7.4 リース・レンタル・シェアリングモデル
7.5 導入パッケージ:機器+ソフト+サービス契約
7.6 用途別採用ドライバー・障壁・ROI比較
8 地域別市場分析
8.1 地域区分(北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ)
8.2 北米市場:規模・主要作物・企業動向
8.3 欧州市場:施設園芸密度・補助金・認証制度
8.4 アジア太平洋市場:人手不足・施設園芸拡大・輸出連携
8.5 中南米市場:価格弾力性・導入段階・拠点化戦略
8.6 中東・アフリカ市場:農業近代化・国際協力案件
8.7 地域別市場規模・成長率・導入ステージ比較
9 競争環境とバリューチェーン
9.1 バリューチェーン(部材・機器・ソフト・サービス・運用)
9.2 市場プレイヤーのタイプ:プラットフォーマー/機器専業/ソフト・AI専業/サービスプロバイダ
9.3 主要企業プロファイルと参入動向
9.4 提携・M&A・技術ライセンスの状況
9.5 競争優位性分析(技術、サポート体制、データ蓄積、スケーラビリティ)
9.6 競争マトリクス:製品/価格/サービス/地域展開
10 価格・収益モデル・TCO分析
10.1 機器価格帯(作物別・規模別)
10.2 サブスクリプション/成果連動モデルの構成
10.3 ライフサイクルコスト(導入+運用+保守+更新)
10.4 収益源(収穫効率改善、労務削減、ロス低減、夜間稼働)
10.5 価格モデルとマージン構造(機器 vs ソフトサービス)
10.6 コスト削減事例とベンチマーク
11 導入プロセス・オペレーション
11.1 導入ロードマップ(パイロット→スケール→フリート)
11.2 圃場診断と改修(樹形調整、照明補強、配列最適化)
11.3 運用体制(夜間シフト、保守パターン、教育)
11.4 データ運用(収穫データ分析、改善サイクル、ダッシュボード)
11.5 KPI監視・維持メンテナンス・アップデート戦略
12 導入リスク・課題と対応策
12.1 作物・規格・環境の変動によるモデル誤差
12.2 作物遮蔽や複雑樹形・傾斜等の物理的チャレンジ
12.3 溶媒・農薬・洗浄・衛生要件との兼ね合い
12.4 資金・補助金・リース条件の変動リスク
12.5 保守・部品・サービスネットワークの整備状況
12.6 リスク軽減方法(モジュール化、冗長化、データバックアップ)
13 技術・市場将来展望
13.1 短期(1-2年):施設園芸向け部分自動収穫の普及拡大
13.2 中期(3-5年):果樹園・露地栽培向け自律収穫ロボットの実装加速
13.3 長期(5-10年):フリート運用・完全自動収穫・需要価格連動制御の実現
13.4 クロスセクター展開(物流・積載・選別統合)との融合
13.5 持続可能性・データ駆動型農業・スマートファームの一翼としての位置づけ
14 ケーススタディ・ベストプラクティス
14.1 先行導入事例(いちご施設、トマトハウス、果樹園)
14.2 導入前後のKPI改善:収穫時間、ロス率、可販果率、夜間稼働率
14.3 失敗要因および教訓(設計不適合、メンテ滞り、ROI誤算)
14.4 スケールアップ戦略と普及成功条件
15 付録
15.1 用語・略語一覧
15.2 調査対象企業一覧/機器分類表
15.3 図表一覧/データ表記単位・換算レート
15.4 免責・著作権・再配布ポリシー
※「作物収穫ロボットのグローバル市場(2025年~2029年):製品別(果物・野菜収穫ロボット、穀物収穫ロボット)」調査レポートの詳細紹介ページ
⇒https://www.marketreport.jp/crop-harvesting-robots-market
※その他、Technavio社調査・発行の市場調査レポート一覧
⇒https://www.marketreport.jp/technavio-reports-list
***** H&Iグローバルリサーチ(株)会社概要 *****
・本社所在地:〒104-0033 東京都中央区新川1-6-12
・TEL:03-6555-2340 E-mail:pr@globalresearch.co.jp
・事業内容:市場調査レポート販売、委託調査サービス、情報コンテンツ企画、経営コンサルティング
・ウェブサイト:https://www.globalresearch.co.jp
・URL:https://www.marketreport.jp/crop-harvesting-robots-market