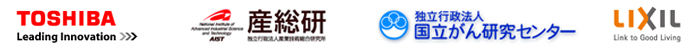2025年11月4日
H&Iグローバルリサーチ(株)
*****「ニューロフィードバックシステムのグローバル市場(2025年~2029年):用途別(注意欠陥多動性障害(ADHD)、疼痛管理、不眠、不安障害、その他)」産業調査レポートを販売開始 *****
H&Iグローバルリサーチ株式会社(本社:東京都中央区)は、この度、Technavio社が調査・発行した「ニューロフィードバックシステムのグローバル市場(2025年~2029年):用途別(注意欠陥多動性障害(ADHD)、疼痛管理、不眠、不安障害、その他)」市場調査レポートの販売を開始しました。ニューロフィードバックシステムの世界市場規模、市場動向、市場予測、関連企業情報などが含まれています。
***** 調査レポートの概要 *****
1.市場全体像と成長背景
(小タイトル:脳科学とデジタル療法の融合による新たなケアパラダイム)
ニューロフィードバックシステム市場は、神経科学・精神医学・認知行動療法・デジタル技術が交差する新しい医療・ウェルネス分野である。脳波(EEG)や機能的近赤外線分光(fNIRS)など神経活動をリアルタイムに計測し、そのデータを可視化・フィードバックすることによって脳機能の自己調整を促す手法である。これまで研究室・クリニック・リハビリセンターなど限られた領域で利用されてきたが、近年はデジタルセンサーの低価格化、AIによる信号解析の自動化、メンタルウェルビーイングへの需要拡大によって商業化が急速に進んでいる。
市場規模は2024年時点で数十億ドル規模に達し、今後2030年まで年平均8〜12%の成長が予測される。主要用途は、①神経発達障害(ADHD、自閉症スペクトラム)、②不安・うつ・PTSD、③慢性疼痛・不眠症、④リハビリテーション(脳卒中後、外傷性脳損傷など)、⑤認知機能向上・スポーツパフォーマンス、⑥ウェルネス/セルフケアである。医療機関・大学研究室・スポーツチーム・家庭用デバイスユーザーなど多層の需要が存在し、従来の医療器市場とは異なるヘルスケアとコンシューマーの境界市場を形成している。
成長の主因は以下の4点に整理できる。
神経疾患・精神疾患の増加:WHOによれば世界のうつ病・不安障害の罹患率は増加傾向にあり、薬物治療以外の非侵襲的介入法への関心が高い。
デジタル療法(DTx)の普及:脳波データを用いた自己制御トレーニングが「科学的根拠を持つデジタル治療」として承認・保険適用を模索する動きが広がる。
AIとセンサー技術の進化:ノイズ除去・特徴抽出・脳波分類を自動化するアルゴリズムの進歩により、専門家がいなくても使用できる。
ウェルビーイング志向の社会変化:ストレスマネジメント、集中力向上、睡眠の質改善など、一般消費者ニーズが市場を牽引。
さらにコロナ禍を経て、遠隔療法・セルフケア機器への信頼が増し、在宅ニューロフィードバックやオンラインセッションが急増したことも市場拡大を後押ししている。
2.技術セグメントと製品動向
(小タイトル:EEGの民主化とリアルタイム脳データの応用拡大)
2-1.EEGベースシステム(主流技術)
現在の市場の約70%を占める主流技術はEEG(脳波)ベースである。電極を頭皮に配置し、脳波の周波数帯域(デルタ、シータ、アルファ、ベータ、ガンマ波など)を解析し、特定の活動パターンを視覚・聴覚・触覚的フィードバックとしてユーザーに返す。目的は、過活動・低活動の領域を「トレーニング」によって最適化することにある。たとえばADHDでは前頭前野のベータ波活性を増やすトレーニングが集中力向上に寄与するとされる。
最新機器では、ドライ電極技術によって装着が容易になり、ワイヤレス通信(Bluetooth / BLE)でPCやスマートフォンにリアルタイム転送可能。加えて、クラウド分析・AIアルゴリズムを通じて脳波プロファイルを自動生成し、トレーニングの個別化が進む。これにより、従来の医療専門家向け装置から、一般ユーザーが扱えるアプリ連携型ウェアラブルへとシフトしている。
2-2.fNIRSおよびハイブリッド型
EEGに次ぐ新潮流がfNIRS(近赤外分光法)やEEG+fNIRSハイブリッド型である。これは脳の血流変化を測定し、活動領域をマッピングする技術で、特に脳卒中リハビリや認知リハビリテーション分野で注目されている。EEGがミリ秒単位の時間分解能に優れるのに対し、fNIRSは空間分解能に優れる。両者を組み合わせることで、時間×空間の双方向解析が可能になり、神経可塑性の定量評価が進む。
2-3.ハードウェアの進化
ハードウェアの小型・軽量化により、ヘッドバンド型・ヘルメット型・イヤーウェア型など多様なフォームファクタが登場している。多チャンネルEEG(32〜128ch)から、日常用途に適した2〜8chの簡易型まで幅広いレンジで展開されている。また、**モーションセンサーや心拍・皮膚電気反応(GSR)**を統合したマルチモーダル型が増加し、脳—身体統合モデルとしての研究応用も拡大している。
2-4.ソフトウェア・解析プラットフォーム
ニューロフィードバックの成否を左右するのは解析アルゴリズムとユーザーインタフェース(UI/UX)である。近年はディープラーニングを用いた脳波パターン分類、集中・リラックス状態のリアルタイム推定、個別最適トレーニング自動設定が一般化。さらに、クラウド接続で多拠点データを統合分析し、研究用プラットフォームとしてオープンAPI化する動きもある。ゲームやVRと連携したインタラクティブ・トレーニングも増えており、「遊びながら脳を鍛える」体験型アプローチが広がっている。
3.応用分野別動向と将来展望
(小タイトル:医療からウェルビーイングへ、データ駆動の脳トレ革命)
3-1.医療・臨床応用
医療用途では、ニューロフィードバックがADHD、不眠症、うつ病、てんかん、PTSDなどへの補助療法として研究・導入されている。米国・欧州では臨床試験データが蓄積し、薬物療法に比べて副作用が少なく、非侵襲・行動変容型の治療法として注目される。特に小児ADHD領域では、認知行動療法や家庭でのモニタリングと組み合わせたハイブリッド治療が普及しつつある。
また、神経リハビリ分野では、脳卒中後の運動機能回復や高次脳機能障害への介入として活用される。神経可塑性を高める目的で、ニューロフィードバックと**脳刺激(tDCS/tACS)**を組み合わせる研究も進行中である。
3-2.メンタルヘルス・ストレスマネジメント
世界的にストレス、不安、うつの管理が社会課題化しており、ニューロフィードバックはマインドフルネス+生理的自己調整を融合したアプローチとして人気を集める。EEGを利用した「ストレスインデックス」「集中指数」などのスコア化により、ユーザーは客観的に自分の精神状態を把握し、呼吸法や瞑想と連動させて改善することができる。企業の社員ウェルビーイングプログラムやスポーツ選手の集中力訓練など、B2B/B2G用途にも拡大している。
3-3.教育・学習分野
教育領域では、注意力・ワーキングメモリ向上を目的とする「ニューロエデュケーション」プログラムが登場。脳波によるフィードバックを授業や学習アプリに組み込み、学習効率を可視化する試みが広がっている。特にADHDや学習障害(LD)の児童への補助教材として活用されるケースが増加中。
3-4.ウェルネス・一般消費者向け市場
家庭向け・コンシューマー市場では、脳波トレーニングヘッドバンドや瞑想支援アプリが登場し、「セルフメンタルケア」領域が拡大している。睡眠改善、集中力向上、リラクゼーション体験などを訴求する製品が主流。特にVR/AR技術を用いた没入型ニューロフィードバックが注目され、リモートワーク時代のストレス緩和やパフォーマンス向上に寄与している。
3-5.市場課題と規制動向
課題としては、①臨床的有効性のエビデンス不足、②標準化されたプロトコルの欠如、③データプライバシー、④規制・認証の不統一がある。医療機器としての承認を得るには、各国規制当局(FDA、CE、PMDA等)の基準を満たす必要があり、医療用とウェルネス用の線引きが今後の市場秩序を決める鍵になる。また、脳データの取り扱いは倫理的にも慎重さが求められ、GDPRやAI倫理指針に準拠した設計が進む。
3-6.地域別動向
北米:最大市場。臨床研究・スタートアップ活動が活発。医療用・民生用の両市場をリード。
欧州:大学・病院ネットワークによる研究主導型。公共補助金と倫理審査が整備。
アジア太平洋:日本・韓国・中国・インドでメンタルヘルス需要が急増。低価格デバイス普及が進行。
中南米・中東アフリカ:心理療法・教育・ウェルネス領域から導入開始段階。
3-7.競争環境と主要企業
市場は中小ベンチャー主体で、米国・欧州を中心に多数の開発企業が存在する。代表的プレイヤーは以下のタイプに分類できる。
医療用デバイスメーカー(臨床EEG・研究施設向け)
ウェルネスデバイス企業(家庭用・アプリ連携型)
ソフトウェアベンダー(解析・クラウド・教育用途)
研究機関スピンアウト(大学発スタートアップ)
主要企業はアルゴリズム性能・装用快適性・価格帯・UIの直感性などで競争。特許ポートフォリオと臨床データの保有が強みとなる。近年は、AI分析企業との提携やデジタル療法企業との統合モデルも増加している。
3-8.将来展望
今後は次の3つの方向で進化が予測される。
パーソナライズド・ニューロモジュレーション:個人の脳活動特性をAIが解析し、最適な訓練プロトコルを自動生成。
ニューロフィードバック+脳刺激の融合:tDCS・TMSなどの電気/磁気刺激技術と統合し、治療効果を増強。
非侵襲・非接触センシング:光学・超音波・fNIRSによる“装着しない”脳モニタリングが研究中。
長期的には、ニューロフィードバックは「自己制御支援AI」としてスマートフォンやヘッドセットに組み込まれ、ストレス・集中・睡眠・感情の常時モニタリングと最適化を行う「ニューロウェアラブル社会」へと進化するだろう。
まとめ(Executive Insights)
科学から実装へ:ニューロフィードバックは研究室段階から商用・臨床・家庭へと拡大し、「脳データを使った行動変容」の基盤技術として位置づけられる。
医療×ウェルネス融合市場:精神疾患からストレスマネジメント、学習支援、パフォーマンス向上まで幅広い応用を持つハイブリッド領域。
AIによる個別最適化:脳波解析・トレーニングパターン生成・行動予測が自動化され、専門家依存度が低下。
規制と倫理が鍵:医療機器承認、データ保護、AI倫理対応が国際市場参入の条件となる。
中長期の可能性:ウェアラブル技術・非接触センシング・メタバース統合によって、脳とデジタル空間を双方向につなぐ新しい産業領域が形成される。
***** 調査レポートの目次(一部抜粋) *****
1.エグゼクティブサマリー
(小タイトル:市場ハイライトと示唆)
1.1 レポートの目的・対象範囲・読者想定
1.2 世界市場スナップショット(市場規模、CAGR、地域別構成比)
1.3 セグメント別ハイライト(技術別/用途別/エンドユーザー別)
1.4 主要ドライバー・抑制要因・市場機会の要約
1.5 規制・償還・倫理ガバナンスの要点
1.6 競争環境の概観(集中度、カテゴリー別主要プレイヤー)
1.7 短期・中期・長期の成長シナリオ(ベース/強気/慎重)
1.8 経営アクションの要点(製品、価格、流通、提携の優先課題)
2.調査設計と方法論
(小タイトル:データソースと予測手法)
2.1 調査アプローチ(一次・二次情報、検証プロセス)
2.2 サンプリングとバイアス低減のための手当て
2.3 市場規模の推計フレーム(トップダウン/ボトムアップ)
2.4 予測モデル・感度分析の前提条件
2.5 為替・デフレーター・価格基準(名目/実質)
2.6 切り口定義(技術、製品、用途、エンドユーザー、地域)
2.7 統計的有意性と信頼区間の取り扱い
2.8 制約事項・限界・アップデート方針
3.市場定義と範囲
(小タイトル:用語・分類・境界条件)
3.1 ニューロフィードバックの定義(EEG/fNIRS/ハイブリッド他)
3.2 バイオフィードバック、デジタル療法、脳刺激(tDCS/TMS)との違い
3.3 医療用途とウェルネス用途の境界(規制上の区分)
3.4 製品構成:ハードウェア、ソフトウェア、消耗品、サービス
3.5 対象疾患・適用領域の範囲(ADHD、不安・うつ、PTSD、てんかん、失眠、疼痛、リハビリ、パフォーマンス向上)
3.6 バリューチェーン(研究・設計/製造/流通/臨床・非臨床導入)
4.市場概観
(小タイトル:需要構造と導入段階)
4.1 導入ライフサイクル(黎明→成長→拡大)と採用カーブ
4.2 需要側構造(医療機関、教育現場、スポーツ、企業ウェルビーイング、家庭)
4.3 供給側構造(専門医療機器メーカー、ウェアラブルベンダー、SaaSプラットフォーマー、コンテンツ提供者)
4.4 収益モデル(装置売り切り、SaaS、サブスク、セッション課金、B2B2C)
4.5 併用・統合トレンド(CBT、瞑想アプリ、ゲーム/VR、脳刺激機器)
4.6 主要ユースケース別の価値仮説と医療経済性
5.市場ダイナミクス
(小タイトル:ドライバー・抑制要因・機会・リスク)
5.1 成長ドライバー
5.1.1 メンタルヘルス需要の構造的増加
5.1.2 センサー低価格化と装用性向上(ドライ電極、軽量化)
5.1.3 AI解析・自動プロトコル設計の普及
5.1.4 遠隔・ハイブリッド提供モデルの定着
5.2 抑制要因
5.2.1 臨床エビデンスのばらつき・標準化未整備
5.2.2 規制・償還の不確実性(医療/ウェルネス境界)
5.2.3 データプライバシー・倫理的配慮の負荷
5.2.4 熟練オペレーターの不足(医療現場)
5.3 市場機会
5.3.1 児童・青年・高齢の年齢別プログラム設計
5.3.2 企業ウェルビーイング・EAPとの連携
5.3.3 教育・学習支援の制度化と公費導入可能性
5.3.4 fNIRS/EEGハイブリッドや非接触センシングの商用化
5.4 リスクと対応
5.4.1 過剰期待・広告誇大化リスクとコンプライアンス
5.4.2 サイバーセキュリティ・クラウド依存リスク
5.4.3 サプライチェーン(半導体・樹脂・物流)遅延
6.技術別市場分析
(小タイトル:EEG中心からマルチモーダルへ)
6.1 EEGベース・ニューロフィードバック
6.1.1 周波数帯域別トレーニング(θ/α/β/γ)
6.1.2 プロトコル(SMR、Zスコア、LoRETA等)の位置づけ
6.1.3 ドライ電極/ゲル電極、チャンネル数のトレードオフ
6.2 fNIRSベース・ニューロフィードバック
6.2.1 空間分解能と臨床適応
6.2.2 アーチファクト対策・計測環境
6.3 ハイブリッド(EEG+fNIRS/GSR/HRV)
6.3.1 多変量解析・機械学習による統合
6.3.2 リアルタイム適応型フィードバック
6.4 新興技術(非接触光学、超音波、近耳道電極 等)
6.4.1 研究段階/商用化ロードマップ
6.4.2 規制・安全基準への適合性
7.製品別市場分析
(小タイトル:ハード・ソフト・サービスの三層)
7.1 ハードウェア
7.1.1 ヘッドバンド型・ヘルメット型・イヤーウェア型
7.1.2 携帯型 vs 据置型、チャンネル構成と用途別最適
7.1.3 アクセサリ・消耗品(電極、キャップ、ケーブル)
7.2 ソフトウェア
7.2.1 信号処理・アーチファクト除去・特徴抽出
7.2.2 ダッシュボード、遠隔モニタ、ガイド付きセッション
7.2.3 開発者向けSDK/API、研究モード
7.3 サービス
7.3.1 臨床セッション提供(クリニック、リハビリ施設)
7.3.2 オンライン指導・ハイブリッドコーチング
7.3.3 B2Bプログラム(企業ウェルビーイング、スポーツ)
8.用途別市場分析
(小タイトル:医療・準医療・ウェルネス)
8.1 ADHD(児童・成人)
8.2 不安症・うつ病・PTSD
8.3 不眠症・睡眠の質改善
8.4 てんかん・神経発達症候群
8.5 慢性疼痛・片頭痛
8.6 脳卒中後・外傷性脳損傷(TBI)のリハビリ
8.7 認知機能向上(注意・ワーキングメモリ)
8.8 スポーツパフォーマンス・メンタルトレーニング
8.9 一般ウェルビーイング・ストレスマネジメント
8.10 教育・学習支援(ニューロエデュケーション)
9.提供モード別分析
(小タイトル:クリニック、在宅、ハイブリッド)
9.1 院内・施設内提供(専門家主導)
9.2 在宅・コンシューマー導入(自己主導、アプリ連携)
9.3 ハイブリッド(初期評価は施設、継続は遠隔)
9.4 遠隔指導・テレヘルス対応の要件(UI、データ共有、同意)
10.エンドユーザー別分析
(小タイトル:誰が使い、誰が支払うか)
10.1 病院・クリニック・リハビリセンター
10.2 心理士・セラピスト・行動療法士
10.3 教育機関(学校、学習塾、大学研究室)
10.4 スポーツチーム・競技団体・軍・警察
10.5 企業(EAP/ウェルビーイング組織)
10.6 個人ユーザー(家庭・パーソナルユース)
11.流通チャネル分析
(小タイトル:直販、代理店、プラットフォーム)
11.1 直販(D2C/B2B)とECプラットフォーム
11.2 医療機器ディストリビューション(規制対応チャネル)
11.3 リセラー/導入パートナー(教育・スポーツ・企業向け)
11.4 サブスク・レンタル・リースモデルの活用
11.5 アフターサービス(キャリブレーション、消耗品供給)
12.地域別市場分析
(小タイトル:規制・償還・文化的受容の差)
12.1 北米(米国・カナダ)
12.1.1 規制・保険償還・臨床導入の進展
12.1.2 主要都市圏での施設クラスターと研究連携
12.2 欧州(西欧・北欧・中東欧)
12.2.1 倫理・データ保護規制(GDPR)と臨床研究ネットワーク
12.2.2 国別の医療制度・導入事例
12.3 アジア太平洋(日本、中国、韓国、インド、ASEAN、オセアニア)
12.3.1 学校・企業・スポーツの採用動向
12.3.2 価格受容性とローカルプレイヤー
12.4 中南米
12.5 中東・アフリカ
12.6 地域別KPI(導入密度、価格帯、チャネル優位、障壁)
13.規制・標準化・倫理
(小タイトル:コンプライアンスと信頼性の基盤)
13.1 医療機器分類・承認要件(各地域)
13.2 ソフトウェア医療機器(SaMD)・アルゴリズム変更管理
13.3 品質マネジメント(QMS/ISO 13485 等)
13.4 データプライバシー・セキュリティ(アクセス制御、暗号化、監査)
13.5 AI倫理・バイアス対策・説明可能性
13.6 臨床評価・RCT・実臨床エビデンス(RWE)
13.7 標準化団体・相互運用性(データ形式、API)
14.価格・コスト・償還
(小タイトル:TCOと費用対効果)
14.1 装置価格レンジ(研究用高機能/クリニック中位/家庭用普及)
14.2 ソフトウェア・サブスク・サポート費用
14.3 セッション料金相場(地域差・提供者別)
14.4 償還スキーム(私費、保険、企業福利厚生)
14.5 費用対効果分析(アウトカム指標、欠勤減、学習効果、再発低減)
14.6 原材料・物流・在庫管理のコスト感度
15.競争環境
(小タイトル:プレイヤーマップと戦略)
15.1 市場集中度(CR4・CR8)とカテゴリー別勢力図
15.2 製品ポジショニング(医療グレード/準医療/ウェルネス)
15.3 差別化要因(精度、装用性、UX、プロトコル数、コンテンツ)
15.4 M&A・提携・共同研究の動向
15.5 価格戦略・チャネル戦略・地域戦略
15.6 SWOT比較(代表企業の強み・弱み・機会・脅威)
15.7 参入障壁(規制、ブランド信頼、臨床ネットワーク、特許)
16.技術トレンドと特許・学術動向
(小タイトル:イノベーションパイプライン)
16.1 信号処理・機械学習の進化(自動適応、個別化)
16.2 多モーダル統合(EEG+fNIRS+HRV+GSR)
16.3 ゲーミフィケーション・VR/AR連携・没入型UX
16.4 長時間装用・非接触化・低消費電力化
16.5 特許出願動向(地域・技術カテゴリ別)
16.6 論文・臨床試験の増加トレンドと注目研究テーマ
17.ESG・サステナビリティ・社会的受容
(小タイトル:責任ある脳データ活用)
17.1 環境負荷(デバイス素材、電池、リサイクル設計)
17.2 社会面(アクセス平等、教育・医療格差への貢献)
17.3 ガバナンス(データ主権、二次利用、透明性)
17.4 インクルーシブデザイン(年齢・障がい配慮)
17.5 ステークホルダー・エンゲージメント(医療者、教育者、家族)
18.市場予測(数量・金額)
(小タイトル:2024–2029 と長期展望)
18.1 世界市場規模・CAGR(価値・数量)
18.2 技術別予測(EEG/fNIRS/ハイブリッド/新興)
18.3 製品別予測(ハード/ソフト/サービス)
18.4 用途別予測(医療指向/ウェルネス指向)
18.5 提供モード別・エンドユーザー別予測
18.6 地域別予測(主要国明細を含む)
18.7 感度分析(価格、規制、採用率、証拠集積の進度)
18.8 長期(2030年以降)のテーマ別展望
19.シナリオ分析とリスクマトリクス
(小タイトル:ベース/強気/慎重)
19.1 仮説設定(規制、償還、技術ブレイクスルー)
19.2 ベースシナリオの前提とKPI
19.3 強気(High Adoption)シナリオのトリガー
19.4 慎重(Low Adoption)シナリオとボトルネック
19.5 リスクマトリクス(影響度×発生確率)と回避策
20.戦略提言
(小タイトル:プレイヤー別アクションプラン)
20.1 機器メーカー向け:設計ロードマップ、差別化KPI、価格戦略
20.2 ソフトウェア/SaaS事業者向け:UX、データ保護、相互運用性
20.3 医療・教育提供者向け:導入プロトコル、評価指標、人材育成
20.4 企業・公的機関向け:ウェルビーイング導入、評価体系、費用対効果
20.5 投資家向け:技術トレンド、規制イベント、エグジット観点
21.主要企業プロファイル(抜粋フォーマット)
(小タイトル:定型テンプレート)
21.1 企業概要(設立年、拠点、従業員)
21.2 製品・サービス(装置、ソフト、プロトコル)
21.3 技術差別化(アルゴリズム、特許)
21.4 臨床・研究連携(試験、学術提携)
21.5 地域展開・チャネル・提携ネットワーク
21.6 財務・資金調達・M&A
21.7 SWOTと今後の注力分野
22.ケーススタディ・導入事例
(小タイトル:実装と成果)
22.1 病院・クリニック:ADHDプログラムの再入院抑制
22.2 教育現場:学習効率・集中指標の改善
22.3 スポーツ:競技パフォーマンスの可視化と介入
22.4 企業:ストレススコア低減と生産性向上
22.5 在宅:遠隔コーチングによる継続率改善
23.データディクショナリと指標定義
(小タイトル:KPIの標準化)
23.1 信号品質、セッション時間、遵守率(アドヒアランス)
23.2 臨床アウトカム(症状スコア、睡眠、注意、機能評価)
23.3 経済指標(費用対効果、欠席・離職、教育成果)
23.4 安全性・副作用・苦情の指標
23.5 プライバシー・セキュリティKPI(イベント、MTTR)
24.付録
(小タイトル:参考情報と用語)
24.1 略語集・用語集(EEG、fNIRS、SMR、RWE等)
24.2 図表一覧(市場マップ、技術比較、プロトコル例)
24.3 調査票テンプレート・インタビューフロー
24.4 参照文献の範囲と更新履歴
24.5 免責事項・著作権・再配布条件
※「ニューロフィードバックシステムのグローバル市場(2025年~2029年):用途別(注意欠陥多動性障害(ADHD)、疼痛管理、不眠、不安障害、その他)」調査レポートの詳細紹介ページ
⇒https://www.marketreport.jp/neurofeedback-systems-market
※その他、Technavio社調査・発行の市場調査レポート一覧
⇒https://www.marketreport.jp/technavio-reports-list
***** H&Iグローバルリサーチ(株)会社概要 *****
・本社所在地:〒104-0033 東京都中央区新川1-6-12
・TEL:03-6555-2340 E-mail:pr@globalresearch.co.jp
・事業内容:市場調査レポート販売、委託調査サービス、情報コンテンツ企画、経営コンサルティング
・ウェブサイト:https://www.globalresearch.co.jp
・URL:https://www.marketreport.jp/neurofeedback-systems-market