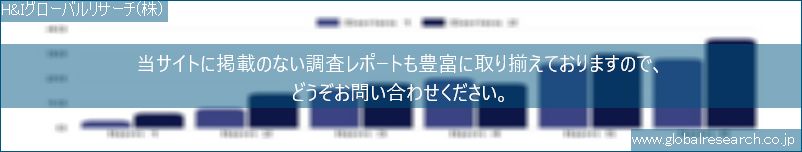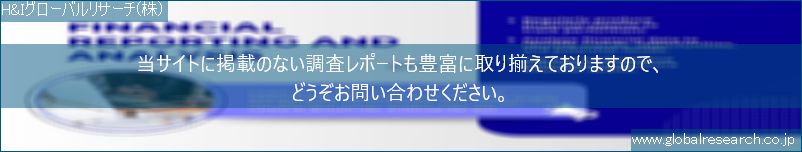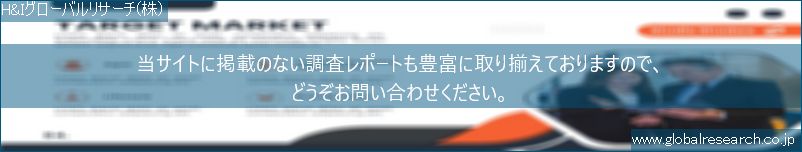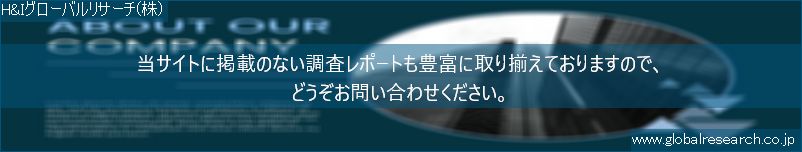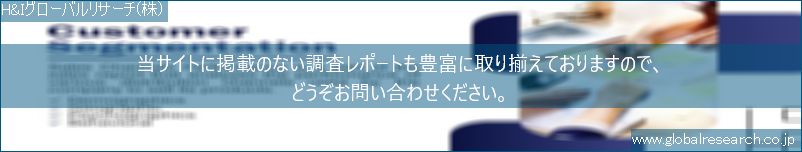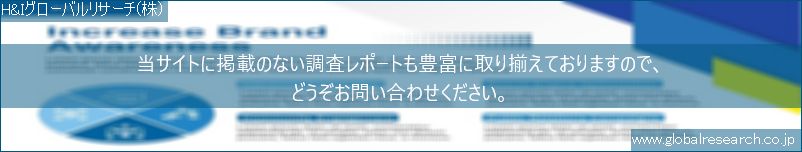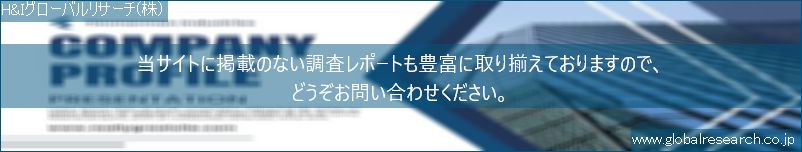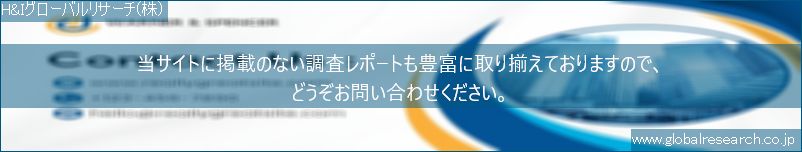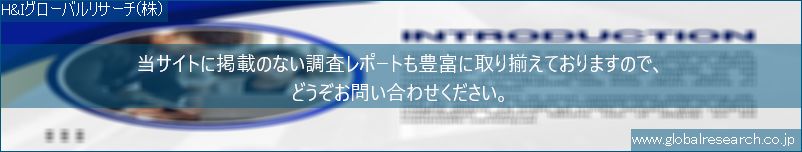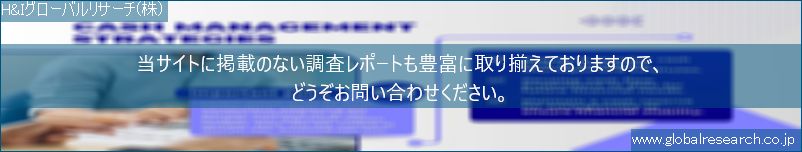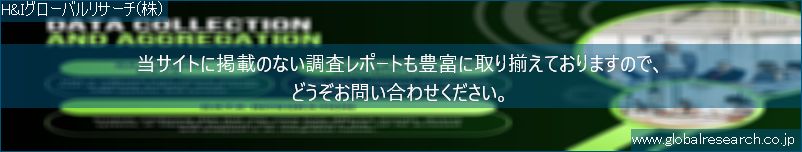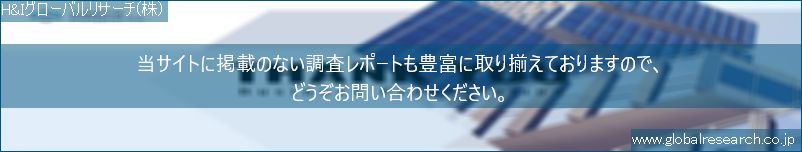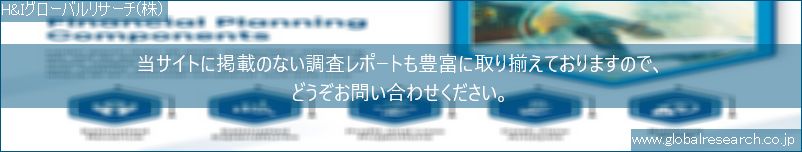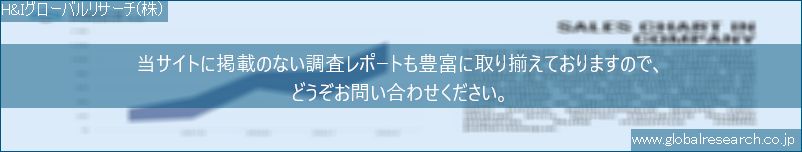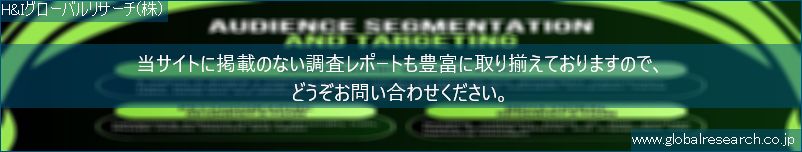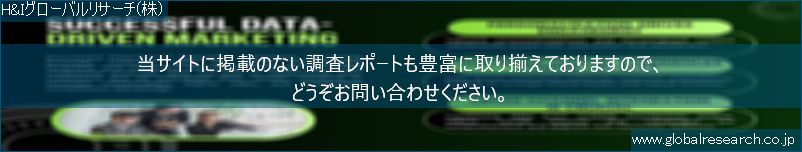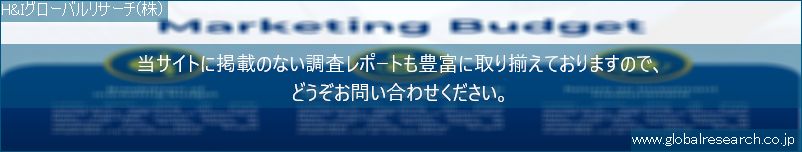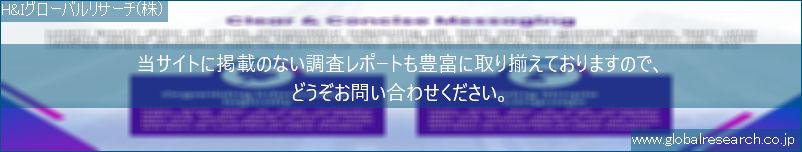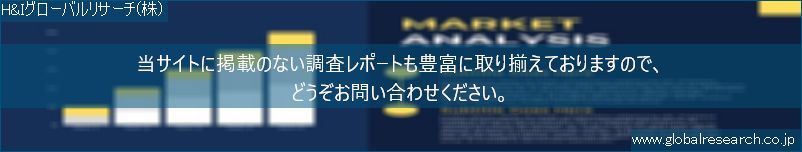日本のコンドミニアム&アパートメント市場規模は2024年に5,430万ドルに達した。IMARC Groupは、2025年から2033年にかけての成長率(CAGR)は6.37%で、2033年には9,880万米ドルに達すると予測している。都市化、ライフスタイルの変化、投資誘致、人口動態の変化、建設技術革新など、いくつかの要因の普及が進んでいることが、主に市場成長の原動力となっている。
コンドミニアム&アパートメントは、どちらも複数の住戸を持つ集合住宅であるが、所有形態が異なり、ライフスタイルも異なることが多い。アパートは通常、1つの建物内にある賃貸住戸で、通常は法人または個人が所有し、入居者は所有者に賃料を支払う。アパートは、プール、ジム、共同スペースなど様々なアメニティを備えた大規模な複合施設の一部であることもあり、入居者はメンテナンスや修繕の責任を限定的に負うことになる。逆に、コンドミニアム(マンション)は、建物内の一室を個別に所有するものである。コンドミニアムの所有者は、特定の住戸の権利証を所有し、多くの場合、共用部分やアメニティの所有権を共有する。コンドミニアムの所有者は、共有スペースの維持・運営のために自治会費を支払い、売却することも含め、賃貸アパートの所有者に比べ、自分の住戸をより自由に管理することができる。コンドミニアムはコミュニティ感覚を提供することができ、豪華な設備が付いていることが多い。コンドミニアム&アパートメントの違いは、どちらも住居として機能するものの、主に所有権、責任、ライフスタイルのアメニティに左右される。
日本のコンドミニアムとアパートの市場動向:
日本のコンドミニアム&アパートメント市場は、都市化と大都市圏における住宅需要の高まりを主な要因として、急成長を遂げている。都市部の人口が増加し続けるなか、一般に手頃な価格でメンテナンスの手間が少ないマンションへの需要が大幅に加速している。さらに、ライフスタイルの嗜好が変化し、職場や教育機関、アメニティ施設に近接した都心部に住みたいという志向が高まっていることも、コンドミニアムとアパートの両方の需要を後押ししている。さらに、共同生活への需要と嗜好の高まりが、共用設備や共同体感覚を提供することの多いコンドミニアムの魅力を高めている。同時に、有望なリターンや住宅市場の安定性に後押しされた不動産投資の急増が、日本におけるマンションとアパート両方の開発の触媒として作用している。さらに、単身世帯の増加や住宅取得を遅らせる人々によって特徴づけられる人口統計の進化が、賃貸マンションへの傾向を際立たせている。これとは別に、持続可能で効率的な建物の開発を可能にする建設技術の進歩が続いていることも、日本のコンドミニアム・ アパートメント市場を牽引すると予想される。
日本のコンドミニアム&アパートメント市場のセグメンテーション:
IMARC Groupは、2025年から2033年までの国別予測とともに、市場の各セグメントにおける主要動向の分析を提供しています。当レポートでは、市場を種類別に分類しています。
種類別インサイト
– コンドミニアム
– アパート
本レポートでは、種類別に市場を詳細に分類・分析している。これにはコンドミニアム&アパートメントが含まれる。
地域別インサイト
– 関東地方
– 関西/近畿圏
– 中部地方
– 九州・沖縄地方
– 東北地方
– 中国地方
– 北海道地方
– 四国地方
また、関東地方、関西・近畿地方、中部・中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方といった主要な地域市場についても包括的に分析している。
競争環境:
市場調査レポートでは、競争環境についても包括的に分析しています。市場構造、主要プレイヤーのポジショニング、トップ勝ち抜き戦略、競合ダッシュボード、企業評価象限などの競合分析がレポート内で取り上げられています。また、すべての主要企業の詳細なプロフィールが提供されています。主要企業には以下の企業が含まれます:
– 旭化成ホームズ株式会社(旭化成株式会社)
– 鹿島建設
– ミサワホーム(株ミサワホーム株式会社
– 中野建設株式会社
– 日本ハウスホールディングスミサワホーム株式会社
– パナソニック ホームズ日本ハウスホールディングス株式会社(パナソニックホールディングス株式会社)
– 積水ハウス株式会社
– 住友林業積水ハウス株式会社
– タマホーム積水ハウス
– ヤマダホームズ住友林業
本レポートで扱う主な質問
– 日本のコンドミニアム&アパートメント市場はこれまでどのように推移してきたか。
– COVID-19が日本のコンドミニアム&アパートメント市場に与えた影響は?
– 日本のコンドミニアム&アパートメント市場の種類別内訳は?
– 日本のコンドミニアム&アパートメント市場のバリューチェーンにおける様々な段階とは?
– 日本のコンドミニアム&アパートメント市場における主要な推進要因と課題は何か?
– 日本のコンドミニアム&アパートメント市場の構造と主要プレーヤーは?
– 日本のコンドミニアム&アパートメント市場における競争の程度は?
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Japan Condominiums and Apartments Market - Introduction
4.1 Overview
4.2 Market Dynamics
4.3 Industry Trends
4.4 Competitive Intelligence
5 Japan Condominiums and Apartments Market Landscape
5.1 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
5.2 Market Forecast (2025-2033)
6 Japan Condominiums and Apartments Market - Breakup by Type
6.1 Condominiums
6.1.1 Overview
6.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.1.3 Market Forecast (2025-2033)
6.2 Apartments
6.2.1 Overview
6.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.2.3 Market Forecast (2025-2033)
7 Japan Condominiums and Apartments Market – Breakup by Region
7.1 Kanto Region
7.1.1 Overview
7.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.1.3 Market Breakup by Type
7.1.4 Key Players
7.1.5 Market Forecast (2025-2033)
7.2 Kansai/Kinki Region
7.2.1 Overview
7.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.2.3 Market Breakup by Type
7.2.4 Key Players
7.2.5 Market Forecast (2025-2033)
7.3 Central/Chubu Region
7.3.1 Overview
7.3.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.3.3 Market Breakup by Type
7.3.4 Key Players
7.3.5 Market Forecast (2025-2033)
7.4 Kyushu-Okinawa Region
7.4.1 Overview
7.4.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.4.3 Market Breakup by Type
7.4.4 Key Players
7.4.5 Market Forecast (2025-2033)
7.5 Tohoku Region
7.5.1 Overview
7.5.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.5.3 Market Breakup by Type
7.5.4 Key Players
7.5.5 Market Forecast (2025-2033)
7.6 Chugoku Region
7.6.1 Overview
7.6.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.6.3 Market Breakup by Type
7.6.4 Key Players
7.6.5 Market Forecast (2025-2033)
7.7 Hokkaido Region
7.7.1 Overview
7.7.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.7.3 Market Breakup by Type
7.7.4 Key Players
7.7.5 Market Forecast (2025-2033)
7.8 Shikoku Region
7.8.1 Overview
7.8.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.8.3 Market Breakup by Type
7.8.4 Key Players
7.8.5 Market Forecast (2025-2033)
8 Japan Condominiums and Apartments Market – Competitive Landscape
8.1 Overview
8.2 Market Structure
8.3 Market Player Positioning
8.4 Top Winning Strategies
8.5 Competitive Dashboard
8.6 Company Evaluation Quadrant
9 Profiles of Key Players
9.1 Asahi Kasei Homes Corp. (Asahi Kasei Corporation)
9.1.1 Business Overview
9.1.2 Product Portfolio
9.1.3 Business Strategies
9.1.4 SWOT Analysis
9.1.5 Major News and Events
9.2 Kajima Corporation
9.2.1 Business Overview
9.2.2 Product Portfolio
9.2.3 Business Strategies
9.2.4 SWOT Analysis
9.2.5 Major News and Events
9.3 Misawa Homes Co. Ltd.
9.3.1 Business Overview
9.3.2 Product Portfolio
9.3.3 Business Strategies
9.3.4 SWOT Analysis
9.3.5 Major News and Events
9.4 Nakano Corporation
9.4.1 Business Overview
9.4.2 Product Portfolio
9.4.3 Business Strategies
9.4.4 SWOT Analysis
9.4.5 Major News and Events
9.5 Nihon House Holdings Co. Ltd.
9.5.1 Business Overview
9.5.2 Product Portfolio
9.5.3 Business Strategies
9.5.4 SWOT Analysis
9.5.5 Major News and Events
9.6 Panasonic Homes Co. Ltd. (Panasonic Holdings Corporation)
9.6.1 Business Overview
9.6.2 Product Portfolio
9.6.3 Business Strategies
9.6.4 SWOT Analysis
9.6.5 Major News and Events
9.7 Sekisui House Ltd.
9.7.1 Business Overview
9.7.2 Product Portfolio
9.7.3 Business Strategies
9.7.4 SWOT Analysis
9.7.5 Major News and Events
9.8 Sumitomo Forestry Co. Ltd.
9.8.1 Business Overview
9.8.2 Product Portfolio
9.8.3 Business Strategies
9.8.4 SWOT Analysis
9.8.5 Major News and Events
9.9 Tama Home Co. Ltd.
9.9.1 Business Overview
9.9.2 Product Portfolio
9.9.3 Business Strategies
9.9.4 SWOT Analysis
9.9.5 Major News and Events
9.10 Yamada Homes Co. Ltd.
9.10.1 Business Overview
9.10.2 Product Portfolio
9.10.3 Business Strategies
9.10.4 SWOT Analysis
9.10.5 Major News and Events
10 Japan Condominiums and Apartments Market - Industry Analysis
10.1 Drivers
Restraints
and Opportunities
10.1.1 Overview
10.1.2 Drivers
10.1.3 Restraints
10.1.4 Opportunities
10.2 Porters Five Forces Analysis
10.2.1 Overview
10.2.2 Bargaining Power of Buyers
10.2.3 Bargaining Power of Suppliers
10.2.4 Degree of Competition
10.2.5 Threat of New Entrants
10.2.6 Threat of Substitutes
10.3 Value Chain Analysis
11 Appendix
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/